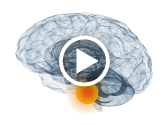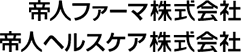ALONE IN MY UNIVERSE
独りぼっちの私〜先端巨大症との戦い
第1章
「診断までとフラストレーション」
ダニエル・ロバーツ
第1章目次
Chap1-1 はじめに
“We learn geology the morning after the earth quake.”
「我々は地震の翌朝に地質学を学ぶ」
ラルフ・ワルド・エマーソン、「処世論」
(Ralph Waldo Emerson、1803年~1882年、米国の思想家、哲学者、作家、詩人、エッセイスト)
実際のところ、私は特にエマーソンの作品に詳しいわけではありません。しかし、このチャプターの序文を探していた時に、この一節を見つけ、先端巨大症の闘病生活をよく言い表していると感じました。先端巨大症と診断される前は、「脳下垂体(pituitary)」という言葉は、私には馬鹿げたもののようにしか聞こえませんでした。漫画のキャラクターが不味い物を吐き出す時に言いそうな言葉だな、なんて思っていたぐらいです。脳下垂体が何なのか、どこにあるのか、何を司っているのかなんて知りませんでしたが、今の私なら、脳下垂体の話の一つや二つぐらいはできます。白衣の医師から「あなたは脳下垂体を手術する必要がある」と聞かされれば、人は脳下垂体について、あっという間に学んでしまうものです。
私の名前はダニエル。32歳です。2002年に先端巨大症と診断されました。診断を受けたのをまるで昨日のことのように鮮明に覚えていて、この病気のことを知ってから8年も経ってしまったのが信じられないぐらいです。私の知っている先端巨大症の患者さんのほとんどは、診断されるまでに長い道のりを歩んでいますが、その道のりには、振り返ってみて初めて気づくものです。私の道のりがどのようなものであったのかを、できるだけ分かりやすく描きたいので、まずは私のバックグラウンドについて少しだけお話しさせていただきます。
難しい病気にかかっている場合、サポートとなってくれる人や物、つまりサポートシステムというものは命綱であり、それは人によって少しずつ異なります。それが何であったとしても、とにかくサポートシステムは必ず持っている必要があります。私はシュナウザー犬を飼っており、ずいぶんと甘やかしているのですが、私自身は今のところ独身で、子どももいません。闘病生活における私の命綱は、両親、祖父母、兄弟姉妹、親友でした。さまざまな理由から、私はこういった人たち以外の人間関係にはあまり時間を費やしてきませんでした。頻繁に転居しては新しい土地での生活を楽しんでいるので、ときには恋愛をすることもありますが、深い関係に発展したことは一度もありません。時折、新しい恋人との関係を考える時、私はいつも自問自答してしまいます。先端巨大症について、いつ彼に話すべきなのかしら? それに、もしも関係がさらに進んで、彼が子供を欲しがった時には、いったいどうすれば良いの? と。正直なところ、こういった事について、どうすべきなのか分かりません。それでも普段は、その日その日を精一杯生きるようにし、今、コントロールできない事については考えないようにしています。色々と力となって支えてくれた素晴らしい友人と家族には、ただただ感謝しています。
さて、私のサポートシステムについて簡単にお話しさせていただいたので、次に、現実的に日常生活ではどのように対処しているのか、ということについて話を進めていきます。人は皆、生計を立てる必要がありますし、私も例外ではないので。大人としての冒険の日々を送る中、私は管理業務で生計を立てていますが、授業を受ける時間とお金があるので大学にも通っています。伝統的なやり方とは言えないでしょうが、そもそも私は伝統主義者ではないので、私にはピッタリです。それに、先端巨大症があるので、医療保険を維持しなくてはならず、フルタイムの仕事を確実に続ける必要があります。いつしかアメリカの医療が、雇用者に頼らなくとも、手頃な医療費で医療が受けやすくなることを願っていますが、とりあえずは、今あるシステムのもとでどうにかしようとしています。
Chap1-2 高校時代──空腹と易疲労感との戦い
それでは、話を少し前に戻し、診断を受けるまでの長い道のりで体験したフラストレーションについてお話しさせていただきます。もしも、あなたも最近になって先端巨大症と診断されていたのだとしたら、気になる出来事や体のどこかがおかしいと感じていたことなどを思い出したりしているうちに、かなりの時間が経っている、なんていうことがあるのではないでしょうか。本当にたくさんの兆候や症状があるので、後になって振り返ればそれが先端巨大症だったと分かるのですが、「あの時」はこれらが病気の兆候や症状であることには、まず気付かないものです。
先端巨大症は、とてもゆっくりと、そしてこっそりと進行する病気です。先端巨大症自体の確定診断も非常に困難なのですが、(高血圧や糖尿病などの)他の病気が既に存在する場合は、先端巨大症の症状を他の病気のせいにされてしまうことがよくあります。私には先端巨大症の他にも苦労していたことがもう一つあり、これが先端巨大症の症状を隠していました―体重です。私は大きな赤ちゃんでしたし、ずんぐりむっくりの子供でした。そして思春期には、体重を減らそうとしなかった時や、ダイエットプログラムの半ばで行き詰ってしまわなかった時を思い出すことができません。中学生の頃は、たぶん20~30ポンド(約9~14kg)程度、太り過ぎているぐらいでした。ただしこれは、地域で行っている運動競技や、学校の活動に積極的に参加していたにもかかわらず、です。しかし、高校1年生か2年生の頃にかなり体重が増え始め、1996年に高校を卒業する頃には、私は病的な肥満体となっていました。たくさん食べた直後にもかかわらず、際限のない空腹感に襲われていた日々を思い出します。どうあがいても、その状況をコントロールすることができないように感じたのです。誤解しないでください、個人の責任については分かっています。私が理解できなかったのは、なぜ、他の人が経験しないような果てしない空腹感を私は感じているのか、ということです。単に食欲を満たしたいという欲望だけでなく、肉体的にも本当に空腹だったのです。ただ食べてばかりではいけないと分かっていたので、満腹ではなくても、食べるのをやめることが多々ありました。満腹感が本来ならばあるはずだ、ということを分かっていたので、非常に苛立たしかったです。他の人には皆、満腹感があるのに、私の場合、満腹感がやって来ないか、すぐにまた空腹になってしまうかのどちらかでした。次第にこの問題は悪化し、体重はあっという間に雪だるま式に増えていったようです。もともと20~30ポンド(約9~14kg)程度、太り過ぎていただけなのが、日々活発に過ごしているにも関わらず、どうすればわずか数年で100ポンド(約45kg)以上も太るのでしょう? すべてを自分自身の行動と選択のせいにされ、どのように改め、コントロールすれば良いのかがどうしても分からない状況に対して、私は何度も何度も自分を責めました。
他の先端巨大症の患者さんも、食欲に関する同じような葛藤を経験しているなんて、1年以上前にアクロメガリー・コミュニティー(Acromegaly Community)のサイトに入るまでは、全く知りませんでした。それまで読んだ物にも、先端巨大症の症状として記載されていませんでしたし、医師がこういった食欲の問題が先端巨大症と関係があると言っているのも聞いたことがありませんでしたし、それに私が尋ねてみても、関係があるとはおっしゃいませんでした。もっとも、時が経つにつれて、先端巨大症については医師もまだまだ勉強している段階であることが分かりました。医師は、目に見えるものや研究できるものについては知っているのですが、私たちが感じていることといったような、観察できないものについては知ることができないのです。先端巨大症の患者さんは全員が肥満体なのでしょうか? いいえ、私は先端巨大症を発症するずっと前から肥満体だったので、先端巨大症が肥満の原因ではなかったことは分かっています。でも、先端巨大症が、思春期から問題をかなり悪化させたのではないか、と確信しています。
私の青春期といえば、学生の頃、ずっと熱烈な「バンドマニア」(ここでの「バンド」とはマーチング・バンドのこと)であったことを抜きにして、この時期の事や先端巨大症の闘病について語ることはできません。「ある時、バンドの合宿でね、…」というセリフは、「アメリカン・パイ」(青春コメディドラマ)が流行らせ、面白いセリフにしたわけですが、そうなるずっと前から私の口から出ていた言葉でした。6歳の頃、家族ぐるみで付き合っていた友人がクラリネットを吹いているのを見た時から、クラリネットを吹きたくなってしまったのを覚えています。一目惚れでした。輝くキーの付いた美しい黒いスティックが、それまでに聴いたことがないほど美しくて独特な音色を奏でていたのです。私が最初に上達し始めた時もなかなか独特な音が出ました。とはいっても、その音が素晴らしかったとか、そういうことはありませんでしたけど。
高校では望み通りの楽器を演奏するだけではありません。38度以上の暑さの中、9kgほどもあるポリエステル製のユニフォームを着て、フットボール競技場でのショータイムのステップを覚えたり、音楽も何曲か暗譜したり、コンテストやパレードで行進したりするのですが、これを全部、毎日何時間も練習しなければなりません。母校が競争に勝つためです。こういったことは大好きでしたが、かなりの時間を取られましたし、へとへとになりました。フットボールの試合、コンテスト、パレードといったもの全てにおいて他の子たちに負けずについて行くためには、他の子の2倍頑張らなければならないと感じていました。競争さえしていなければ、週末に一日中、または二日間とも、ずっと眠っていました。学校から帰宅するなりベッドに倒れこみ、翌朝までずっと眠り続けていたことがありました。この事については誰も何も考えていませんでした。私は活発でした。ティーンエイジャーでしたし、ティーンエイジャーは大いに眠る必要があります。それに私は他の子よりも太っていたので、両親は私が他の子よりも少し疲れやすいのだと思っていました。
私の「バンドマニア」の日々を振り返ってみると、当時、感じていた酷い疲労感とは別に、先端巨大症に関係していたのでは? と思うことが2つあります。1つは、音楽の個人レッスンで、もっと良い音を出すために、顎を突き出させず平らにして、マウスピースに引き戻すよう、先生に何度も指導されたことです。レッスンの間、どれだけ頑張っても、私は顎を平らにすることができませんでした。この顎の飛び出し具合は私にはどうにもできなかったのです。それまで、このような問題はなかったかと思うのですが、あのレッスンでは、この事が苛立たしかったのを覚えています。口の形をどのようにしなくてはならないのか、先生は何度も私にやって見せてくださるのですが、それを一生懸命真似しようとしても、私の顎は思うように動きません。レッスンが終了時間になっていることに先生が気付いた時、とりあえずそこで終わりにして、私に「これを心に留めて練習を続けるように」とだけおっしゃいました。私はできるだけのことをやってみたのですが、骨の柔軟性のコントロールには限度があります。私の顎は、前歯が反対咬合になっていたのですが、私はそれに気づいていませんでした。
「バンドマニア」の日々を振り返って思い当たる、先端巨大症の2つ目の赤信号は靴です。私は太っていたので、他の子たちがバンドのユニフォームやアクセサリーが載っているカタログで注文した標準サイズの靴は、私にはフィットしませんでした。私が履けるほどの幅もなく、また、テキサスの暑さの中でたくさん行進するので、もっとしっかりと足をサポートする靴が必要でした。条件としては、標準的な白い革靴ということだったので、カタログ以外ならもっと自分のニーズに合っている靴を購入することができたのです。母は、素晴らしいウォーキング用・矯正用の靴を手掛ける地元の靴屋さんへ連れて行ってくれました。明らかにそのお店はもっと年齢の高い人向けでしたが、申し分のない白い革のウォーキングシューズが私の足の形によくフィットしました。サイズは81/2WW(25.0cmの3E)で、雲の上を歩くような履き心地! その靴が誰のためにデザインされたかなんて、気にも留めませんでした。マーチング・バンドにいる間は、自分の足に合わせて靴を作ってもらい、毎年、新しい靴を買っていました。高校時代には靴のサイズは変わりませんでしたが、先端巨大症のせいで成長はまだ終わっていませんでした。そのうち、ちょっと恥ずかしい状況になってしまうのですが、それについては後ほど触れるつもりです。
Chap1-3 大学時代──多嚢胞性卵巣症候群
高校卒業後、私は友人たちと一緒に、実家から1時間ほどの距離にあるテキサス州オースティンに引っ越しました。パートタイム学生(1学期あたりの履修単位が12単位未満の学生のこと;12単位以上はフルタイム学生とされる)として大学に通い、管理業務をして自活し、実家から離れ、世の中の若者がよくやるような楽しくてバカなことをするなど、新たに発見した自由を楽しみました。同時に、ラーメンを使ったレシピを物凄くたくさん覚えましたが、これはあの年代の通過儀礼なのだと考えています。オースティンでは4年間過ごしましたが、高校生の頃のように、原因不明の眠気と極度の疲労の日々が続きました。時折、起き上がって動いたりすることもできないぐらい疲れてしまっている日もあり、職場に電話を入れて休まなくてはならないことがありました。私の身体は両極端な感じでした。とても元気で、エネルギーではちきれそうな日があったかと思うと、とてもだるくて疲れ切った状態で、ほとんど何もできない日もありました。勤務先の会社のマネージャーが、様々なビタミン剤やハーブを勧めてくれたので、そのほとんどを試してみたのを覚えています。こういった提案はほとんど効果がありませんでしたが、私はこの疲労感をなんとかしてコントロールしようとしました。そもそも、「どうすれば仕事中に疲れすぎないようになるか」などという助言を上司にしてほしい人なんているでしょうか? 私は若かったですし、そんな心配をする必要なんてないはずだと思っていました。しかし、どんなに頑張っても疲労感を隠すことができない日もあり、苛立たしかったです。いつも順調に仕事をしていることを誇りとしていたので、プロとして悪く思われたくありませんでした。そこで、やはり自分の体重のせいだと考え、体をもっと動かして減量に取り組む必要があるのでは? と考えました。ジムに入会して毎日運動し、食べ物にも、もう少し注意するようにしました。友人とルームメイトの助けもあり、体重は少し落ちました。しかし残念なことに、こういった前向きなライフスタイルの変化にもかかわらず、極度の疲労感は続いていったのです。
私は高校でも1番と言って良いほど太っているほうでしたが、大人になってオースティンに住んでしばらく経った頃、私のように肥満で悩んでいる人たちに出会いました。その時、自分とこの友人たちとの間には大きな違いがあることに気付きました。この友人たちは、私みたいに疲れているようには見えませんでした。それも、あまり活動的でない生活を送っている人でさえ、そんな感じです。私の知る限り、病気だったり、パーティーでお酒を飲み過ぎたり、ということでもない限り、一日中眠っているような人はいませんでした。普通の体形の仲間についてゆくのも、この友人たちにとっては特に大変そうではありませんでした。もっと積極的で責任感のある大人だったら、おそらくこういった事について色々と尋ねたりしたことでしょう。でも、私はただ普通になりたかったわけで、自分の体験していることについて深く話したくはなかったのです。もしかしたら私とこの友人たちとでは体の仕組みが異なっていて、私ももう少し体重を落とすことができれば、この人たちと同じように元気になるのではないかしら、なんて考えていました。
ちょうどその頃、それまでになかったような生理不順と出血過多が現れ始めました。このようなことは高校生の頃にもあったのですが、オースティンにいる間(1996~2000年)に、特に悪化していきました。仕事を通じて医療保険に入っていたので、産婦人科でこの症状を調べてもらうことにしました。この時、初めて多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)という病気を知りました。1998年にこの病気と診断され、かなり色々な事の説明がつくようになりました。ようやく答えにたどり着いたわ! 産婦人科の先生は、多嚢胞性卵巣症候群は、主にインスリン抵抗性物質によって引き起こされ、糖尿病の前兆となる、ということをご説明くださいました。私の体はしばらくの間、体内の血糖を抑えることができるくらいの量のインスリンは出していたわけですが、細胞のほうがしっかりとインスリンに反応していなかったので、血糖をエネルギーにきちんと変えられず、体はさらにインスリンを出し続けている状態だったのです。この病気を持つ女性に現れる症状としては、肥満、にきび、月経不順・出血過多・無月経、多毛(体や顔)、男性型の脱毛、不妊症、疲労といったものが挙げられます。多くの疾患と同様、全ての症状に当てはまらなくても、確定診断はなされます。これらの症状のほとんどに覚えがある私は、多嚢胞性卵巣症候群であることを疑いませんでした。ようやく答えが見つかり、本当に安心しました。
けれども、病気が診断されたことによる安心感はそう長くは続きませんでした。さまざまな問題を引き起こしていたものの正体が分かったのは良かったのですが、多嚢胞性卵巣症候群の治療が、食事療法や運動、その他にメトホルミン製剤(インスリン抵抗性改善薬)やピルの服用もありうる、という点は正直、不愉快でした。この中では、残念ながら運動しかきちんとできず、それ以外はうまくいきませんでした。私は自分の体の大きさがどうであれ、いつも活動的でいるよう心掛けていました。食事療法は永遠の闘いとなっていますが、ピルの服用は体重増加と関係があるとのこと。今、すでに体重との闘いで苦労しているのに、ピルの服用で、さらに大変な思いをするのなら、あまり服用したくないと思いました。メトホルミン製剤も試してみたのですが、吐き気、頭痛、消化不良といった副作用が出たので中止してしまいました。つまり、診断はされたものの、治療はほとんどしなかったのです。今までと同じように過ごし、自分で症状をどうにかしようとしました。
Chap1-4 2000年──肥大していた足
2000年の春には、すでにオースティンからニューハンプシャー州のナシュアに引っ越していました。親友の一人が、その前の年にここに引っ越したのですが、私がオースティンで働いていた会社が大きな財務問題を抱え始めた時期、その親友にここに引っ越すよう説得されたのです。私は21歳で、アパートの賃貸契約の期限も、もうすぐ切れますし、新しく住む所と新しい仕事を探すつもりでした。「こんな時ですもの、ちょっと冒険でもしてみようかしら」なんて思いました。私には失うものなんてありませんでしたから。ニューハンプシャーで臨時の仕事をし、空いた時間には、ホワイト山地へドライブに行ったり、ニューハンプシャー州とメイン州にあるビーチに何か所か行ったり、ボストンを探検したりなどして楽しく過ごしているうちに数か月経ちました。すると突然、ニューハンプシャーに来るよう私を説得した友人に、今度はニューヨーク市場で仕事をするチャンスが訪れたのです。彼はこのオファーを受け入れることにしました。私はナシュアには数か月しかいませんでしたし、1人でここに残るつもりもありませんでしたが、テキサスにも戻りたくありませんでした。ですから、彼と一緒にニューヨークへ移ることにしたのです。最初はニューヨーク市内に住み、ニューヨーク市内で働いていたのですが、最終的には、友人も私も、新しく知り合った友人たちと一緒にロングアイランドの東部にたどり着いてしまいました。正気の人なら、考えもなくこんなことなんてしないと分かっています―でも、21歳で正気の人なんているでしょうか? 不景気とは何なのか、私たちは全く分かっていませんでした。仕事を辞めたとしても、新しい仕事なんていつでも見つかりましたから。実際、私たちはそんなことを繰り返していました。医療保険なんて興味もありませんでした。どうせ私たちには必要のない、単なる贅沢品でしたから。ヒラリー・クリントンが、数年前に大きな騒動を起こしたのはなぜなのか、そして、突然、廃案にしてしまったのはなぜなのか―そんなこと、私たちには全くもって分かりませんでした(当時、ヒラリーは医療保険改革問題特別専門委員会の委員長を務めていた。国民皆保険ではないアメリカに国主導型の健康保険制度を導入しようと、医療制度改革案を1993年に発表した。しかし、大規模な反対活動に遭うなどの理由から、結局、翌1994年に廃案となっている)。私たちは、単にそこで暮らして、働いて、思う存分楽しんでいました…そして私は、眠らなくてはならない時は眠っていました。
ロングアイランドでの楽しみの中に、リバーヘッドにあるアウトレットストアに出かけることがありました。初めて訪れた時は、わけが分からなくなりました。そこにあったんですよ! 私が「バンドマニア」時代に靴を買っていた靴屋さんが! ロングアイランドに? そんなことってあるの? オーダーメイドを行っている靴屋で、サンアントニオにだけお店があったのですが、私の思い違いだったのでしょうか。本当に同じ会社であるかを確かめるため、このお店に行ってみたのですが、間違いありませんでした。私が引っ越して来たことを、このお店がどうやって知ったのか分からないですし、それにここ数年、ずっとここの靴を買いたかったので、まさしく私のためにロングアイランドに店を出してくれたみたいで嬉しかったです。まったく、本当に凄いサービスです! ニューヨーク中をたくさん歩き回ったので、あの素晴らしい履き心地の靴をもう一足、自分に買ってあげたくて、うずうずしました。
車にガソリンを入れたり、駐車したり、靴を買ったりする時、私はたいてい自分でやるのですが、このお店では、店員さんがお客さんの足に靴を履かせたいみたいです。素敵な女性の店員さんに、以前、このお店のサイズで81/2WW(25.0cmの3E)のウォーキングシューズを持っていたことを伝えました。すると、美しくて、ぴかぴかで、白いウォーキングシューズと靴べらを持って来てくれました。見るだけでクラクラしてしまいました。この店員さんが私に履かせようと靴を準備している間、一緒に楽しく話していたのですが、私の足がこの靴に入らないと気付いた瞬間、店員さんの口が止まってしまいました。靴のサイズが私の足に合わなかったのです。それも、全然近いサイズではありませんでした。私は彼女を見てクスクス笑いながら、間違ったラベルが貼られているか、箱が間違っているのではないかしら、と言いました。店員さんは、もっと大きなサイズを勧めてくれましたが、私は何年間もここの靴を買っていましたし、正確なサイズも覚えていました。私があまりにも頑固だったので、店員さんはもう1つの8 1/2WWサイズと、「念のために」と10WW(26.5cmの3E)のウォーキングシューズを持ってきました。結局、どのサイズ買うことになったかを想像してみてください。
信じられません! まず、私の大好きな地元テキサス州の靴屋さんは、サンアントニオ以外、さらにはテキサス州以外にもあるのだ、ということ! 実際、それは私がテキサスとは全く正反対に感じるような州にあったのです! それから、この会社の靴の作り方は変わってしまって、全サイズが以前より小さくなってしまったこと! 一体どうしっちゃったっていうの? 私は思っていることを口に出してしまうたちなので、店員さんが10WW(26.5cmの3E)のウォーキングシューズをレジに通している時、こういったことを冗談混じりに話しました。皆さんは、まるで自分が精神病患者で、相手が少し怖がっているかのようにビクビクしながら笑ってきたり、こわばった微笑みを向けられたりしたことはありますか? 可哀そうな店員さん! そもそも彼女は年配の方だったのですが、お店に若い人がやって来て、矯正用の靴を見てワクワクするといった状況に遭遇したことなんて、まず無いのでしょう。ここまでだけでも奇妙なのに、それだけでなく、自分の靴のサイズを認めたがらず、靴会社が製造基準を変えた、などと話をでっちあげるような人に話を合わせなくてはならなかったわけです。どうりで、私を気違いのように見てきたわけです!
Chap1-5 2002年──顔つきの変化と視覚障害
2001年12月までロングアイランドに住んで、働いていました。もっとここに居たかったのですが、テロ事件があった影響で、地域経済(そして、ゆくゆくは国家経済)が急激に悪化していきました。ここに来て、また、自分の勤めていた会社が倒産間近となってしまい、新しい仕事を見つけるのに苦戦していました。さらに、友人と一緒に借りていた家を家主が売りに出すと決めてしまい、家賃が自分に払える金額で、ペットと一緒に住めるような場所が他に見つかりませんでした。当時、もう一人の親友がダラス/フォートワースにいました。どうやら、新しいルームメイトを探す予定があり、仕事を探すのも手伝ってくれるとのこと。そこから私の実家までは車で4時間の距離だったので、週末に家族に会いに行くこともできました。そんなわけで、テキサスに戻る(異なるエリアではありますが)と決めたのは当然の流れでした。2002年1月、私はダラス/フォートワースに移り、ホテルの販売・ケータリング部門で新しい仕事を始めました。
新しいアパートに落ち着いた頃、週末にサンアントニオまで行き、家族に会ってきました。まず、ハグをして、みんなとの再会で盛り上がりました。それがひと段落すると、母がかなり長いこと私の顔を凝視してこう言ったのです。「顔が変わったわね。お父さんの家系の顔になってきているみたいね。」この言葉に、身が凍りました。自分でもそんな気がしていたのです。でも、自分の想像に過ぎないと思っていました。そういえば、ニューヨークを去る数ヵ月前に同僚の結婚式で撮った写真を見て、それがどうしても自分の顔だと思えなかったのを覚えています―とは言っても、あれが自分の顔だと分かってはいたのですが。自分自身に「カメラの角度がおかしかったに違いない」と言い聞かせました。そういえば、鏡の中の自分を見て、「なんだか鼻が大きくなっていて、上のほうで眉毛に繋がっているあたりに少ししわがあるなぁ。」と思ったこともありました。前はもっと滑らかで平らな顔だったはずです。実際、私の顔は全体的に比較的平らでした。でも今、鏡で横顔を見てみると、今度は三日月形をしているのです。昔の私はいつも二重顎ぎみでしたが、鏡の中の私はもう二重顎でさえありませんでした。
母の言葉を受けて、私はこういった出来事について思いをめぐらし、しばらくの間、黙ってしまいました。父親の家系がどのような外見だったかはよく知っていましたし、誰も今の私のような顔つきではありません。それでも、鼻が大きくなっただとか、顔が変わってしまっただとか言うのは馬鹿げています。人生、歳を取れば、外見が変わっていくものですし、歳とともに受け入れなくてはならないことだって出てきます。誰だって歳なんてとりたくないでしょうけど、折り合いをつけなければならないのです。私が母に言うべきことは、私も顔の変化に気付いていたけど、単に歳を重ねただけだ、ということでした。私も母も、私の顔の変化と父方の家系とは何の関係もないことは分かっていたのだと思いますが、常識的に考えて、外見の変化は年齢あるいは遺伝が原因であり、母は遺伝のせいだと考え、私は年齢のせいだと考えたのです。しかし、結局は二人とも間違っていました。
2002年3月、私は仕事でコンピューターの画面が見えづらくて苦労していたのですが、それはホテルの同僚が気付くほど顕著になっていました。また、毎日が頭痛との戦いで、鎮痛剤を毎日飲んでいることに気づきました。これが何とも不愉快な日課となってしまい、どうにかして止めたいと思っていました。私は眼鏡が必要であると考え、検眼士の予約を取りました。どうやらその判断は正しかったようです―実際に眼鏡が必要でした。左目が乱視、右目が近視でしたが、この問題は、1時間ぐらいで解決しました。新しい眼鏡に慣れるには数日かかりましたが、それでも慣れたので、私は今まで通りの生活を続けました。けれども頭痛は止まることがなく、そして1ヵ月も経たないうちに、再びコンピューターの画面が見えづらくなってしまいました。
ちょうどその頃、私はまた尿路感染症にかかり、治療のために診療所に行かなくてはなりませんでした。ニューヨークでの仕事とは違い、幸い、ここでの仕事では、福利厚生として医療保険が与えられていました。職場の同僚は、皆、同じ医師に診てもらっていたのですが、近くですし、皆が薦めるので、そこで診てもらおうと思いました。診療所では初診の患者として受付してもらい、初診の患者には必ず行う精密検査をしてもらいました。私は頭痛について説明しましたが、検査で血圧が少し高いことが分かりました。頭痛は高血圧と関係のある軽度のものだ、とのこと。医師は、眼鏡を除外すると、頭痛の原因はたぶん高血圧だろう、と言いました。血圧の薬と尿路感染症のための抗生物質、それに多嚢胞性卵巣症候群が糖尿病に進展していないかどうかを確かめるための血糖値測定器が出されました。抗生物質はバッチリ効いて、尿路感染症は治りましたし、2週間血糖値を測定した結果、私はまだ糖尿病でないことも確定しました。また、高血圧の薬は私の血圧を正常範囲のやや低い位置にまで戻しました。それでも、毎日の頭痛は残っていました。
数ヵ月が経過しましたが、私はできるだけ普通に生活し、働き、行動するようにしていました。しかし、そうすることが困難になり、「何かがおかしい」という思いから抜け出すことができませんでした。だいぶ疲れていて(それもいつもより酷い疲れで)、仕事ではどんどんコンピューターの画面が見えづらくなっていきました。8月初旬頃には強烈な恐怖を体験しました。私は職場から家まで高速道路を運転していたのですが、突然、物が二重に見えたのです。それも、ただの複視ではありません。あたかも万華鏡のように、見えている物が動いて見えるのです。目眩を起こし、気持ち悪くなりそうでしたが、何よりも、高速道路で事故を起こすかもしれない、と死ぬほど怖くなりました。繰り返し掌で頭を叩きました。目を思い切り開けてからぎゅっと閉じるのを、できるだけ早くやってみました。それでも止めることができません。とにかく祈りました。どうやったか覚えていませんが、どうにか無事に家にたどり着きました。この出来事のストレスから解放されると、私は正面玄関を抜けて行き、ソファーに倒れてしまいました。そして、ペットの小さい犬を抱いて、ただただ泣きました。たった今起こったことがとても恐ろしく、これはもう無視できないと思いました。
翌日に目覚めたときには複視はありませんでしたが、まだパニック状態でした。職場に休む旨を連絡し、検眼士に電話をして、できればその日に診てほしいと伝えました。幸い、その日の診療枠になんとか入れてもらえました。しかし、あまり踏み込んだ検査はしませんでした。検眼士から片目を隠す黒いプラスチックの遮眼子を渡され、視力検査表を左から右に読んでいきました。どちらの目を覆っていても、見えたのは、私が座っている位置から見て、表の半分だけでした。見えていないもう半分はぼやけて見えているのか尋ねられましたが、私は「他の半分が全く見えません」とハッキリと言いました。黒くしか見えなかったのです。遮眼子を離し、座っている位置から両眼で検査表を見て、私は初めて全体を見ることができました。検眼士は何度か、最近頭を打ったかどうか訊いてきましたが、私は「いいえ」(前日に高速道路で、自分で頭を叩いたのを除けば)と言いました。検眼士のところでは複視の原因は分かりませんでしたが、2~3日後に眼科の先生に診てもらえるよう予約を入れてくださいました。検眼士は、私の眼に何か深刻な病気があれば、眼科の先生がさらに検査して、原因を発見し、治療してくれるはずだ、とおっしゃいました。
Chap1-6 2002年8月──下垂体腫瘍(脳腫瘍)発覚
2002年8月20日のこと。眼科の待合室には、一般的によくある様々な目の疾患について書いてある資料が置いてあったので、私はそれを読んで座っていました。自分がこれらの恐ろしい疾患のどれにかかっているのか? と考えていたら、不安でいっぱいになってしまいました。失明するの? 眼の手術をしなければならないの? 手術中は眼を開けていなくてはならないのよね? 手術はレーザー? それともナイフ? 物凄く痛いのかしら? 手術に失敗して、片目を失ってしまったとしたら、どうなってしまうの? どれくらいの間、仕事できないの? また複視になったら、どうするんでしょう? 私はなぜこのことをまだ誰にも話していないのかしら? 診察室に呼ばれるまでの私は、心配の塊以外の何者でもありませんでした。幸いにも、眼科の先生は非常に冷静で、安心感を与えてくれるような人だったので、検査が始まる頃には、私はもう少しリラックスできていました。
検査は、午前中、1~2時間だけの予定だったので、その後は仕事に戻れると思っていました。すると、瞳孔を開いたうえで、予定より多くの検査を行う必要があるので、午後もお休みすると職場に伝えるように言われたのです。これ以上お休みをいただくことには気が引けましたが、先生に、仕事より健康が大事なのだから、ここに残って検査をしなさい、とはっきり言われてしまいました。職場に電話をかけた後、瞳孔を拡大してもらい、それが効くのを待ってから、さらに検査をしました。数時間後、先生は様々なプリントを持ってやって来て、視野検査の結果から何を調べる必要があるのかが分かった、とおっしゃいました。私の前に出された紙には、2つの円が描かれていたのですが、これが私の視野でした。それぞれの円は、半分は黒く、もう半分は白くなっていました。
先生は、黒い部分が完全に視野を失ったところだと説明なさいました。私は口をぽかんと開け、これが何を意味するのかを理解しようとしているうちに、顔は混乱で歪んでしまいました。 「知らないうちに半盲になったということですか?」 「これまでにも何か兆候があったかと思いますが、その通りです。左右の眼は互いに視野を補い合っているので、片目で見る習慣でもない限り、どれだけ視野が欠けたかなんて気付かないものですよ。」
先生はさらに、視野欠損や複視の原因は、視交差近くにある脳下垂体の腫瘍による可能性が高い、と説明を続けられました。腫瘍が大きくなると視神経を圧迫するので、とりわけ視野欠損と複視が起きるようです。少なくとも先生はそう話していたように記憶しています。私に唯一聞こえたのは「腫瘍」でした。しかも、先生の手振りからだと、腫瘍は頭の中にあるようです。失明や眼の手術かなんて、もうどうでもいい! 私は死ぬんだわ! 脳腫瘍の患者は皆、そうでしょ? 死んでしまうのよ! 頭を剃られ、化学療法と放射線療法を受け、激しく嘔吐して死に至る。映画からこうした脳腫瘍の知識を植えつけられていた私は、脳腫瘍患者が回復したシーンを一度も見たことがありませんでした。どれくらい長い間、そんなことを考えていたか分かりません。家族にも何て言おうか悩みました。
先生が話している間、私は頭の中が真っ白でした。スヌーピーのマンガに出てくる教師のように、ただ「ワーワーワー」と話しているように聞こえていました。先生の話についていこうとしましたが、色々な考えが頭を駆け巡ります。唯一、気付いたことは、先生の話し方が死の宣告をしているような雰囲気ではなかったということ。こんな状況にしては、少しばかり軽い感じだったのです。何かが違っていました。数分経ち、再度、説明を理解しようとしました。この状況について、先生がなぜ、もっと深刻な口調で話していなかったかを理解しなくてはなりません。すると、先生が「良性」という言葉を発するのが聞こえたのですが、それに対して、私は全くおかしな反応をしてしまいました。急に笑い出し、それを抑えることができなかったのです。それは私が覚えていたテキサスの大学ジョーク-「農大の医学用語集」のせいでした。このジョークは、「レッドネック(無学の白人労働者)」や「ブロンド(金髪)」のジョークをネタにしており、テキサスに長く住めば、必ず耳にするものです。 「良性(benign;ビナイン)―8歳になった後(つまり9歳 = “be nine”;ビナイン)になるもの!」
私の顔からは涙が流れ落ち、ゲラゲラと笑っていました。あの靴屋の店員さんがついてなかったと思っていたら、あれは序の口だったわね! その日の大半を検査に費やしたことと、この1週間の出来事の件もあり、私は完璧におかしくなってしまいました! これだけ色々あれば、おかしな感情の爆発がどこかの時点で必ず起きたでしょうけど、私の反応は他の人とは少し異なっていたのでは、と考えています。しかし、私の目の前の人は科学者であり、しかも、とても良い人だったので、私の寒いジョークに付き合うよりも、私が次に何をするべきかについて話してくださいました。
私が自分を取り戻すと、腫瘍を摘出する手順について説明なさり、視力を完全に取り戻せる可能性が高い、とおっしゃいました。そして、医療センターに電話をし、1時間以内にMRI検査が受けられるよう手配してくださいました。同時に、神経内科と内分泌内科に、翌日の受診予約を入れるよう、受付係に指示していました。診療所を出る前に、私は腫瘍を放っておいたらどうなるのですか、と尋ねたのを覚えています。まったく馬鹿げた質問ですが、手術がとても怖かったので、もし何もしなかった場合の最悪のシナリオを知りたかったのです。やはり、人は常に選択肢を比較検討するべきですし、それに、腫瘍は良性でしょ? 私はただ、眼科の先生が話したことをするのが怖かったのです―恐ろしい! 私は先生を困惑させてしまいました。信じられない、といった面持ちで私を見て、「いったい全体、なぜ手術を受けないなどと言うんですか」と尋ねました。正直なところ、後になって考える時、先生が私を診療所から追い出さなかったことには驚きます。幸いなことに、この先生はとても辛抱強く、あの時点で推定される腫瘍の大きさから考えて、手術を受けないなどという選択肢はあり得ない、と説明なさいました。そして、受付まで見送ってくださり、術後に視野を再確認するために受診予約を入れるようにおっしゃいました。私はうなずいて診療所を後にしました。
Chap1-7 確定診断と術前治療
眼科の診療所から近くの病院の放射線科までは10分ほどで着きました。MRI検査を受ける心構えができるよう、この検査がどんなものなのか、簡単な説明を受けました。すると、いつの間にか私はこの機械のベッドに上がっていて、ヘッドホンをあてられ、頭が動かないように固定具を付けられていたのでした。私はハンニバル・レクター(「レッド・ドラゴン」、「羊たちの沈黙」、「ハンニバル」、「ハンニバル・ライジング」に登場する人物。人を食べてしまうため、顔にマスクを付けているシーンがある。)になった気分でした。放射線技師はMRIのトンネルの中に私を突っ込みました。見上げると、細い青い線が端から端へ引かれていて、この線が私を二等分するのを想像しました。その他は全て白く、壁が私を取り囲んでいました。私はそこにいることが信じられず、全てが悪夢であることを祈りました──本当は腫瘍なんて無くて、そして、この棺桶みたいな奇妙な機械にだって本当は入っていないんだ、ということを。ヘッドホンから技師さんによる簡単な指示と説明が聞こえた時、涙が顔を滴り落ちました。すると今度は、私の好きなラジオ局を尋ねてきたので、私は局番を思い出して伝えようとしました。その時は一時的に恐怖とネガティブな考えがまぎれました。しばらくかかりましたが、きちんと思い出し、私がよく聞いていた地元のラジオ局の局番を伝えました。数分の内にヘッドホンから音楽が流れてきました。これにはとても感謝しました。検査の間、少しリラックスできましたから。私が閉所恐怖症になりそうでも、なんとかならずに済んだのは、音楽もありましたが、私の頭の固定具についていた小さな鏡のお蔭でもありました。この鏡はトンネルの外側に傾いていたので、自分の足と検査室の中を少しだけ見渡すことができました。当時、この2つがあるということが、どれだけ恵まれていることかなんて分かっていませんでしたが、それ以降、何年もMRI検査を受けてきましたが、こういった工夫をしてくれていたのはこの病院だけでした。
音楽が流れていてもMRIはうるさかったです。途中で何度か音が変わるのですが、どの音からも振動を感じました。細くて青い線や鏡に映る自分の足を見ていても特に面白くなかったので、目を閉じて、できるだけリラックスすることにしました。検査が半分終わったところで技師さんが入ってきて、私をトンネルから半分ほど出すと、腕に造影剤を注射しました。最初は少し冷たく感じ、次にほんの少しの間、口の中で金属味を感じました。でも、それ以外は、特に変化はありませんでした。私は、合計約45分、トンネルの中にいました。その後、頭は固定具から解放され、検査室から出してもらえました。翌朝、神経科に行くことになっていますが、その時には神経科の先生のもとにMRIの写真と報告書が届いていることでしょう。
家までの運転は苦痛でした。病院を出た頃はラッシュアワーだったので、高速道路はとても混んでいました。私は精神的にも身体的にも疲れ切っていました。家に戻って布団の中にもぐり込み、この世から身を隠してしまいたかったです。あと、私は母に会いたくなりました。いまだに母にこのことを話していませんでしたが、残念ながら、電話越しで伝えなくてはなりませんでした。
母に電話をしましたが、母と継父(この人が、私が「お父さん」と呼ぶ人物ですが、自分の父親とも、素晴らしい関係にあります。父親が二人もいて、私は恵まれているのです。)の外での素敵なディナーの邪魔をしてしまいました。二人の時間を台無しにしたくはなかったので、母に、1時間後に再度電話する、と伝えました。けれども母は私の声から何かを察したのでしょう。その場で、何のために電話したのかを言いなさい、と強い調子で言ってきました。どのように伝えれば良いか考えてしまい、私はしばらくためらっていましたが、その努力は無駄でした。この強烈な一日で、大きなダメージを受けていたので、思わず、「私、両目とも半盲で、脳腫瘍があるの」と言ってしまいました。当然、電話の向こう側でもしばらくの沈黙。それから「今、何て言った?」と聞こえてきました。私はその日に起きた全てを話しました。もちろん、二人とも気が動転し、いろいろ訊いてきたのですが、私には答えが分かりませんでした。眼科での私はあまりしっかりしていなかったので、先生が教えてくださったこともあまり覚えていませんでしたし、脳下垂体腺腫がどのようなものなのかも、まだインターネットで調べていませんでしたから。それに、もっと詳しいことを教えてくれる医師にも診てもらわなくてはなりませんでした。二人には、何か分かったら連絡する、と言いました。あの時を振り返り、自分のこの切り出し方を思い出すと、罪悪感にかられてしまいます。両親は、私が日々不安だったことも、何度も医師に診てもらっていたことも、何も知りませんでした。私自身、二人にはこういったことについて、何も話していませんでした。それなのに私は突然電話をして、楽しいディナーの真っ最中に、このような爆弾を落としたのです。250マイル(約400km)以上離れた場所にいる両親は、心配したり完全に無力感を感じたりする以外、何ができたでしょう?
翌日、朝一で神経内科の先生に会うと、先生は眼科の先生が言った通りのことをおっしゃいました。脳下垂体には直径およそ3cmの大きな腫瘍があり、海綿静脈洞というところに広がっているとのこと。先生は、海綿静脈洞に腫瘍が広がってしまっていることに強い懸念を持っていらっしゃるようでした。私は先生が何をおっしゃっているのか分かりませんでしたが、先生は診察室にMRIの写真を持ってきて、ディスプレイに貼り付け、腫瘍と海綿静脈洞を示しました。先生は、海綿静脈は頸動脈がある所なので、腫瘍がそこに入っていると手術で腫瘍を完全に取るのは難しい、とおっしゃいました。頸動脈にこんなにも近い所を手術するのは、あまりにも危険だからです。先生は、一般的な神経学的な検査を続けましたが、他の機能と反応に関しては全て正常であるようだと分かり、感心していらっしゃいました。通常、あれほど大きな腫瘍では、もっと多くの異常があるそうです。ですから私の場合は、術後、視野が回復するかもしれない、とおっしゃいました。先生は私に内分泌内科に予約を入れているかどうかを尋ねられたので、私はその日の午後に予約があることを伝えました。すると今度は、手術をしてくださる神経外科の先生を紹介してくださいました。
その日の午後に内分泌内科の先生に会いました。この先生はかなりの時間を割いてくださいました。私は自分の症例がどれだけ珍しいのかを全く知りませんでしたが、先生はご存じでした。先生は主に糖尿病と甲状腺が専門でしたが、私の症状に特別な関心を持ってくださいました。後になって、実は3ヵ月ほど前に、もう一人、先端巨大症と診断された患者さんを治療されていたことを知りました。今思うと、この先生が脳下垂体の症例に関心を持ち、私ともう一人の患者さんのために少し勉強してくださっていたことがどれほど私にとって幸運だったかに気付かされます。奇妙ではありますが、私たちは、ある意味、面白かったのです──日頃、ここにやって来る患者さんとは全く違っていましたから。先生は、私に非常に詳細な病歴を尋ね、血液に関しても今まで見たことの無いほどたくさんの検査をなさいました。助手の方が真空採血管6本分も採血したのです! 先生は最初から先端巨大症を疑っていましたが、他の可能性を除外しなければなりませんでした。その中には、血液検査ではできない項目がありました。24時間蓄尿する容器を手渡され、蓄尿したものを検査室に持って行ったのを覚えています。記憶が正しければ、これはコルチゾールの異常を検査するものだったのですが、私はこれがとても嫌でした。もっと酷い検査もあるのは分かっていますが、誰が1日中尿の入った容器を持ち歩きたいでしょうか? 診察室から出る前に先生は、1週間後には検査結果が出るので、何が問題か分かる、とおっしゃいました。見つかった異常によって治療も変わってくるようですが、おそらく、何かしらの薬物療法を受けることになる可能性が高いようです。そうこうしているうちに、神経外科に電話なさり、私の予約を早めようとしていらっしゃいました。凄いわね! 検眼士、眼科医、一般開業医、神経内科医、内分泌内科医、そして今度は神経外科医…彼らの間で、自分がピンポン球になったように感じました。しかし、それはただの始まりに過ぎなかったのです。
ほとんどのアメリカ人はHIPPA法(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)に関して、少なくとも何となくは分かっていて、個人の医療情報に関するプライバシーが保証されることを知っています。しかし残念なことに、何よりもまず、自分の雇用について、そして医療情報による仕事への影響について心配しなくてはなりません。腫瘍と診断され、私もどの情報を職場と共有すべきかを考えなくてはならなくなりました。ここのところ、診察のために既に何日かお休みをいただいていますが、今後もそういうことになります。それだけでなく、脳の手術も受けるのです。風邪で数日休むよりも長くなります。他の人はこんな状況で職場にどんな情報を共有するか分かりませんし、全てのケースに当てはまる解決策が無いことも分かっていますが、私にとっては何から何まで話すことが一番だ、と思いました。私を評価してくれる素晴らしい人たちと仕事をしていましたし、私たちはまるでプロの集団の「家族」のようでしたから。私は彼らに対して正直に全てを説明することが一番良い選択肢であると分かっていました。職場に戻ると、まず、マネージャーと話をしにいきました。ありがたいことに、私は正しかったのです。マネージャーとチームの皆は、私の大きな支えになって、それまでに分かっていた診療予約に合わせて、勤務スケジュールを柔軟に調整してくれたのです。同僚はさらに、私の自己負担額の足しになるようにと、少しばかり寄付もしてくれました。彼らこそ、私がこれまで一緒に働いてきた中でも最高のメンバーであると、今でも思っています。
その後も数週間にわたり、診察は増えていきました。初診、フォローアップ、さらに多くの診療科への紹介、といった感じです。神経外科の先生は彼と組む耳鼻咽喉科の先生を紹介しなくてはなりませんでした。手術で、唇と鼻の切開と縫合が必要だからです。この耳鼻咽喉科の先生が見たかったものがMRIには写っていなかったので、CT検査も受けなければなりませんでした。幸いなことに、CTの機械はMRI装置のように狭くなく、MRIよりも断然早く終わりました。神経外科と耳鼻咽喉科の検査が終わり、予定を調整した後、手術の日取りは9月中旬に決まりました。そうこうしているうちに、内分泌内科の先生は私が先端巨大症であると確定診断を下しました。私のIGF-1の値は1181ng/mLでした。基準値は250以下だったはずなので、これは極端な異常値です。先生は、心臓の状態を調べ、私が手術を受けられるかを判断するために、私を循環器内科に紹介しました──またまた検査です。さらに、大腸内視鏡検査のために消化器科にも紹介なさいました。先端巨大症は大腸癌の危険因子でもあるからです。色々あり過ぎて私が参ってしまっていたのを知ってか、大腸内視鏡検査は脳下垂体の手術の後でも良いと言ってくださいました。さらに、手術の前に腫瘍を縮小させ、IGF-1を抑制するために1日3回の注射を開始することになりました。その注射の仕方を覚えるための診療もありました。
こうなってくると、私の生活は病院と診療に振り回されるようになり、仕事や友人や楽しみといったものは二の次となりました。私はくたくたに疲れていましたし、手術を受けるのを恐れていましたし、意気消沈していました。それに、注射をした後は、いつも吐き気がして横になって休まなければならなかったので、私は注射を毒のように感じていました。そんなこんなで、生まれて初めて、友人たちが物凄くねたましく感じられました。私にも友人たちと同じく若さはありましたが、私にはない健康がねたましかったのです。私が直面していることに友人たちは直面する必要がないことに腹が立っていました。彼らは、何の心配もなく、仕事や学校に行ったり、遊びに出かけたり、私たちの年頃の人たちがやるようなことを普通にすることができるのです──少なくとも、単位を落としたり、仕事で問題に巻き込まれたりする、といったこと以上に深刻な心配をする必要はないのです。私なんて、あの嫌な注射で1日に3度も気分が悪くなる上に、脳の手術を受けなくてはならないのに…。私は、手術が終わっても目が覚めないことや、何か良くないことが起きることを恐れていました。友人たちは支えてくれようとしましたが、これがどんな感じなのかは分かっていませんでした。かつては自分もそうでしたが、友人たちが駆け回って、やりたいことをやって、生きているのを当然のことと思っているのを目にするのは、どれだけ苦しかったでしょう。いつもの私なら、人に嫉妬したりしませんし、自分に与えられている恵みに感謝することを常に心掛けていました。でも、あの時の私は感謝どころではなかったのです。こういった感情はできるだけ隠すようにしました。いつも惨めな人となんて誰も一緒にいたくないでしょうし、自分がどのように感じていたにしても、友人たちのサポートは必要でしたから。
親友の中に、他の人たちよりも自由にスケジュールを調整できる人がいて、この友人に手術まで何度か診療に同伴してもらうことができました。当時、これがありがたいことだとは特に感じていませんでしたが、彼が一緒にいてくれることは掛け替えのないサポートでしたし、診療の苦痛を和らげてくれました。彼は良き「だらだら」仲間であり、どんな状況でも面白いことを見つけることができるのです。診療に私たちが一緒に行くと、他の患者さんやスタッフの方はイライラしていたに違いないと思いますが、このような深刻な状況では、だらだらしたり、笑ったりして緊張を解きほぐす必要がありました。神経外科の待合室で自分のMRIの写真を持って座り、同じくMRIの写真を持っていた他の患者さんを見回し、私たちは、他の患者さんたちはどこが悪いのか、どんな外傷や病気があるのかを勝手に考え、おかしな作り話をしたものです。検査室に入ると、友人は引き出しの中をすべてチェックし、そこにあった器具を出してはそれで遊んでいました。彼が器具について何も知らなければ知らないほど、それを何に使うのか考えているのを見ているのが面白かったです──こんなことをしている最中に医師や看護師がやって来た時は、特におかしかったです。私たちは一緒に医師の話を真剣に聞くのですが、その後で、私がきちんとした質問を考えつかないうちに、友人がおかしな質問をして、私たちほどユーモアの良さが分かっていない医師の前で、二人でゲラゲラと笑ってしまうことが時々ありました。「笑いは一番の薬」とは、うまいことを言ったものです。まあ、笑いの魔法が腫瘍を無くすことはないので、それが一番の薬であるとは完璧には言えませんが、確実に薬に耐える助けにはなりました。
Chap1-8 腫瘍摘出術を受ける
手術までの1週間、私は考えつく限りのありとあらゆる準備をしました。まず、手術についてネットで調べ、脳下垂体腫瘍の患者のグループを見つけ、手術についてチャットしました。そして、仕事を通して、短期障害給付金の申請をし、承認してもらいました。職場には休暇をとる期間を伝え、私の代わりに、以前その職場で働いていたことがあり、スケジュールにも余裕のある友人が臨時スタッフとして働けるよう手配しました。また、病院のICUを見学し、そこのスタッフに会い、手術が終わった後、どんな流れになるのかを教えてもらいました。遺書も完成させ、家族への情報として、私の資産と借金についてと、無いとは思いますが、万一、私が死亡した場合に生命保険がどのように分けられるべきかについても、そこに記しました。さらに、手術の際に両親が滞在できる場所を手配し、滞在中、その周辺で両親が行きそうな場所への行き方を書いたものも準備しました。そしてこれが最も重要なことですが、できるだけ心理的にも心構えができている状態にしました。手術を受けることと、その後に起こり得ることを受け入れたのです。しかし、手術の2日前に、もう一つの大きな問題にぶつかることになるとは思いもしませんでした──手術前の血液検査の結果です。
私の記憶が正しければ、医師は一般的に手術の24時間前に術前の血液検査をします。その項目の中にはPTTと呼ばれるものがありました。この頭文字が何の略なのかは、この検査が何を意味するかに比べれば、それほど重要ではありません。これは基本的に血液がどれくらい早く凝固するかを調べる検査です。血液が凝固するのが速すぎ、凝固の速度を遅らせるために抗凝固薬を投与しなくてはならないケースがある一方で、血液がなかなか凝固せず、手術中の大量出血を心配しなければならないケースもあります。私の場合は後者でした。神経外科の助手さんが手術前日に電話をかけてきて、PTTが異常値のため、翌日に手術することはできない、と知らせてきました。まるで、ジェットコースターが急なところを一気に下っていった時のように、お腹が下に下がるような感じがしました。それって、どういうこと? 今度は血液に問題があるわけ? 今度は何をしなければならないの? いつ手術を受けることになるの? すでに仕事のお休みをいただいているのよ! 今、まさにこの時、両親はサンアントニオから車でやってくるところなのに! 助手さんは謝るしかなく、翌朝に診てもらえるよう手配した血液内科の先生を紹介しました。なんてすごいこと! これでも、まだ私には医師が足りないから、もう一人加えよう、というわけね! この時点で、私は1年以上前から禁煙していました──高校3年生の頃から2001年の8月まであった悪い癖でしたが、体からタバコが抜けてからは、あの癖がぶり返しそうになることなんて本当に一度もありませんでした。しかし、神経外科の助手さんが電話をしてきて、翌日に手術ができないと告げた時は、禁煙して以来で1番、タバコを吸いたい衝動と懸命に闘いました。
翌日、母が血液内科の診察に付き添ってくれました。もっと色々な検査をするということで、この間よりもたくさん血液を採られました。PTTが異常値になる原因について少し話し合うために、血液内科の先生に会いました。すると母が、もしかしたら自分の家系の遺伝形質が原因かもしれない、と先生に伝えたのです。母は、自分の家系は血友病(出血しやすく、血液がなかなか凝固しない病気)ではないものの、フィブリノゲン(血液の凝血因子)の値が遺伝的に低いのだ、と説明しました。先生は、低フィブリノゲンでPTTに異常が起きることは確かにあり、それも検査している、とおっしゃいました。母は私を見て、私がこういった問題に直面しなくてはならず、また自分がこの問題を早く思い付かなくて申し訳ない、と言いました。私は母を非難しませんでした。普通に生活している母に、このようなことを、どうすれば想像できたというのでしょう? 私はただ母がそこにいることに感謝していました。先生は、翌日には検査の結果が出るので、次に何をしなくてはならないのかは電話で教える、とおっしゃいました。先生からの電話は、母が言ったことを裏付けました。私もフィブリノゲンの値が低いこと、そして大量に出血しないよう手術の前に輸血を行う必要があることを告げられました。神経外科の先生は、どうやら血液内科の先生と連絡を取っていたようでした。神経外科の助手さんから電話があり、新しい手術の日付を伝えてきました──2002年10月7日です。
さて、申請した期間に短期障害給付金を貰って休みを取ることはできなくなったので、今まで準備してきたことを、手術までの間、いくつか元に戻さなくてはなりませんでした。ここでもまた、同僚は完璧にサポートとなり、理解してくれ、予定の変更に合わせてくれました。それは、友人たちも、短期障害給付金の会社も同様でした。両親も休みを再度調整してくれました。そして私は、手術への心構えをもう一度しなくてはなりませんでした。医学界は全体として、日常的に大きな医学的な問題に対応することに慣れ過ぎていて、患者が大きな治療を受けるために準備をしなくてはならないことについてはあまり考えていないのではないか、と思うことがあります。こういったことによって、もたらされる精神的ショックは、こういったことを実際に経験したことのない人たちに言い表すことはできません。私は、お年寄りがなぜ手術や病気について、たくさん話をするのかが分かるようになりました。これは闘いなのです。(身体的にも、精神的にも)大きな苦痛を伴い、怖いものなので、何とか乗り切ると、この闘いについて話をするわけです。このことに気付いた時、私は、今度は自分が年寄りになって、自分の闘いについて話をして、若者を退屈させてやりたい、と思いました。
手術前夜、両親は病院に付き添い、受付を済ませ、輸血をしている間、一緒にいてくれ、面会時間が終わると帰っていきました。手術のための麻酔を受ける前の朝一に、両親は戻ってきてくれました。その夜はよく眠れなかったことぐらいしか覚えていませんが、眠れないのは、あの状況から考えると当たり前のことでしょう。朝には、手術の準備をするために色々な人たちがやって来て、私の回りでばたばたとしていました。私は移動式のベッドに上がり、青いキャップを被され、移動して行く時に、両親にさよならのキスをしたのを覚えています。私は、それが両親を見る最後の時ではないことを祈りました。手術室で手術台に上がった時、私の腕には1本の点滴チューブが入っていました。手術室には、麻酔科医の他、耳鼻咽喉科医、神経外科医、あと、私がこれまで一度も会ったことの無い人たちがいました。彼らは医学用語で話していたので、何を話していたのか、ほとんど理解できませんでした。実際、分かる必要なんてありませんでした。数秒のうちに麻酔科医は私の顔にマスクをかぶせて、私に10から逆に数えるように言いました。いくつまで数えたかは分かりませんが、彼らが私の頭の中をほじくっている間、私の意識は飛んでいました。
手術前の祈りにも関わらず、目を覚ました時は、手術の間に死んでいれば良かった、と思ってしまいました。顔が恐ろしく痛みましたし、酷い頭痛もありました。それに、麻酔で気持ち悪くなり、吐きそうにもなっていました。脚にはカーフポンプ(ふくらはぎをマッサージして血栓を予防する装置)が装着されており、下半身からはカテーテルが出ており、点滴の薬剤につながっている絡まったチューブが両腕に刺されており、指には酸素モニターが付けられており、右手にモルヒネポンプを持たされていました。鼻の奥の傷を閉じるための脂肪組織を採るために切開した跡が下腹部にありました(少なくとも、脳神経外科の先生は、そのようにするとおっしゃったように思います)。中心静脈に点滴を入れようとして失敗した首の近くには、テープが貼られていました。スタッフの人たちは、一斉に私に話しかけようとしているようでした。その中の一人が、私の頭に被せてあるキャップを外し、私の太く茶色い巻き毛がとても美しい、と言ってきました。吐きそうになっていなかったら、たぶん彼女に罵りの言葉を叫んでいたことでしょう。あの瞬間、私は美しいとだけは、到底、感じられませんでした。誰かが点滴に、吐き気止めを注入すると、すぐに吐き気は治まったのですが、痛みと不快感は良くなりませんでした。モルヒネポンプが何なのかが分かったとたん、私は気が狂ったようにボタンを押しました。痛みから逃れるために必死だったのです。何日かの間は、意識が飛ぶことだけが唯一の救いとなっていました。たまに目覚めて、しばらく意識がある状態に耐えることができても、めまいがして気持ち悪くなるので、目を閉じなければなりませんでした。分かったことは、私の視野は完全に回復したということ。光や周りで起きていることが全て視界に入って来るのには参りました。
24時間の間、食べたり飲んだりすることができませんでしたが、口が非常に乾燥していて、とても気持ち悪かったです。ミントの香りのする液体に、棒の付いた小さなスポンジが何本か浸してあったのですが、このスポンジを唇にこすりつけたり、少しだけスポンジを吸ったりすることで、口の違和感を軽減することができました。部屋には誰かしら、少なくとも1時間に1度は、私に何かをするために入ってきたように思います。手術の翌朝、術後の脳下垂体がどうなっているかを見るためにMRIをすることになりました。手術の前もMRIが不快だと思っていましたが、手術から回復している時のMRIは、本当に不快でした。それでも、なんとか切り抜け、手術が成功したことが明らかになりました。海綿静脈洞を除いて、腫瘍はどこにも見られなかったのです。自分が困難から脱するのには、まだ程遠いことは分かっていましたが、これは良い知らせだったので、私は大喜びでした──少なくとも、再び意識が飛んでしまうことを望む以外に何か考えられるとしたら、そう感じたことでしょう。
私はトータルで5日間入院していました。ICUで3日間過ごした後、一般病棟で2日間過ごしました。ICUに3日間いるほど悪かったわけではありません。私がICUから出て大丈夫になっても、一般病棟のベッドに空きが無かったのです。手術というものは私にとってこれが初めてで、ここ数日の出来事はたくさん覚えています。ひどい不快感は別として、これまでに感じたことの無いほどの完全な無力感を感じたのを、よく覚えています。体は何かにつながっていないところなんて無かったので、動きたくても、あまり動けませんでした。私に本来あるはずのつつましさなど、無くなっていました。係の人が1日に1度か2度、濡れたタオルを持ってやって来て、私の体を拭き、体の色々な所を見て、清潔になっているか、感染を起こしていないか、きちんと機能しているかを確認するのでした。私の症例には何の関係もない医師や医学生が私を見に来ることに母がうんざりしてしまい、彼らに退室するように言ったのを覚えています。私は毎晩、ある看護師に会うのを楽しみにしていました。彼は私を、ベッドに横になっている患者の一人としてではなく、一人の人間として見て、話しかけてくれたからです。このような状況に置かれると、人は尊厳と人間性を失ってしまいがちなので、自分が正常であることを気付かせてくれる人はだれでも、どんなものよりも貴重なのです。少しだけエネルギッシュで元気に感じる日もあれば、次の日には疲れてしまい、ほぼ1日中寝ていることもありました。ついにベッドを出て歩こうとした時には、自分の身体に裏切られました。私はいつものように起き上がることができると勘違いしていたのです。ベッドで4日間も横になっていたので、看護師と母の助けがなければ、倒れていたことでしょう。あと、鼻には丸めたガーゼが入っていました。退院の直前に、ガーゼを取り出してくれたのですが、それは手品のようでした! リボン状のガーゼがどんどん出てくるのです──本当にこんなにたくさん鼻に入れたわけ? 鼻の中に、こんなにスペースがあるなんて思ってもみませんでした!
合併症に関しては、私はかなり幸運でした。髄液漏も感染もなく、頭痛も2~3日後には耐えられるぐらいになっていました。実は、酷い頭痛を引き起こしていたのはモルヒネだったので、3日目にはモルヒネからペチジンに切り替えなくてはなりませんでした。でも、ペチジンを投与されたのは1日だけで、その後はヒドロコドン配合薬に切り替えました。私に起きた唯一の合併症は、尿崩症でした。これは腎臓が水を保持することができない状態ですが、脳下垂体の手術の後にはよく起きるそうで、通常は一時的なもののようです。私の場合は、1週間しか続きませんでした。手術後、最初の2~3日はとても惨めだったのを別にすれば、回復は順調で、退院してから3週間後ぐらいには、完全に元気に感じました。もちろん、術後の診療はまだありましたが、それも次第に治まるでしょう。
Chap1-9 腫瘍摘出術、術後経過
手術が過去のものになったところで、視野が完全に回復していることを確認するため、再度、眼科に行きました。数時間検査をした後、先生は喜んだ様子で、視野が完全に戻っていると教えてくださいました。別に先生に教えてもらう必要なんてなかったのですが、記録に残すことが重要だと感じていたのでした。また、大腸内視鏡検査を予約するために、消化器の先生にも連絡をとりました。これは極めて普通の検査でした。検査の前の日の夜、「きれいにする」ためにドロドロした透明な液体を大量に飲まなければならず、うんざりしました。そして翌朝、母が私を病院に連れて行ってくれました。受付すると、私は点滴を入れられ、意識を飛ばされました。目が覚めると、部屋にいる誰かが、今までに聞いたこともないような不愉快で大きな音のおならをしていたので、ぞっとしました。「すいません」とも何とも言わないのです! すると、部屋には私しかいないことに気付きました。看護師さんが入ってきたのですが、非常に恥ずかしかったです。おならをコントロールできないわけですから! 看護師さんは、これは自然なことですし、出さなくてはならないですよ、と言いました。大腸内視鏡検査のために、大腸に空気を入れたので、それを出さなくてはいけないらしいのです。問題ないわ! 私は30分の間、おならマシーンになっていました! 看護師さんに神の祝福を! どうしてこんな仕事に就く人がいるのか、私には分かりません! 病院から出してもらった後は、すっかり普通の1日を過ごしました。あれが楽しい経験だったとは言えませんが、それでも、これまでに経験した最悪のケースからはほど遠いものでした。結果は1週間以内に出て、全て正常でした。私の年齢を考えると、7年から10年は再検査の必要はないでしょう。
次に、フォーカスしなくてはならなかったのはホルモンです。これが大腸内視鏡検査ぐらい簡単なものだったら良かったのですが…。脳下垂体の手術を受けた患者さんは皆、脳下垂体の機能を失うリスクがあるので、そうではないかを確認しなくてはなりませんでした。幸い、私の脳下垂体は機能していることが検査結果で明らかになりました。私のIGF-1も他の先端巨大症の患者さんと同じように、術後に正常化するのでは、と僅かながらにも期待を寄せていたのですが、そうではありませんでした。薬物療法無しの状態で700 ng/mL。1181 ng/mLからすると大きな進歩ですが、基準値には程遠い値でした。そこで、腫瘍と副作用をコントロールするために、1ヵ月毎の注射を始めることになりました。打ってから1週間は副作用で不快でしたが、それでも、1日3回の代わりに1ヵ月に1回で済むのは、とてもありがたかったです。効果はあったのですが、時間が経つにつれ、その効果が無くなってしまったので、先生は薬の量を増やしました。すると、前と同じように効果が出るのですが、IGF-1の値は基準値に入りませんでした。あの頃はこの薬に代わる治療薬がまだ治験段階にありましたし、昔からある錠剤は、教えてもらった限りですと、副作用も酷く、効き目もあまり無いようなので、この錠剤を別にすれば、この注射が唯一の薬でした。けれども1年もしないうちに他の薬が出たので、1ヵ月1回の注射から、新しく出た1日1回の注射に切り替えました。この切り替えにはワクワクしませんでしたが、新薬では目立つ副作用が出ず、前よりも元気になったようなので、ありがたかったです。ところが、やがて、新薬でさえも私のIGF-1の値を正常化しなかったことが分かりました。次に、この2剤の併用療法に進みましたが、この治療は全然楽しいものではありませんでした。毎月の注射を行うために、いつも医師に診てもらわなくてはなりませんでした。これは不便ですし、針がとても太くて嫌でした。さらに、毎日の自己注射も続けなくてはならなかったわけですが、両方の薬を併用できたのはこの月だけでした。アメリカの医療制度の弊害が、先端巨大症を持つ私にとうとう襲いかかってきたのです。
手術の約1ヵ月後、名前を聞いたことがある所からも、ない所からも、治療に関係したあらゆる医療機関から請求書が届きました。保険は結局、あまり医療費をカバーしてくれなかったのです。私は払えるだけは払いましたが、今後も繰り返し診療を受けなければならない医師には確実に診てもらえるようにして、あとはほとんど払いませんでした。これはひどい選択ではありましたが、私にとって唯一の選択肢でした。そして、例の薬です。両方とも特殊で非常に高価な薬だったので、保険会社は「事前承認」と呼ばれるものを要求してきました。毎月、保険会社から事前承認を得なければならず、これは毎月戦いでした。多くの保険会社と同様に、あの頃、私の保険会社でも、調剤給付と医療給付の運用を分けることになり、下請けの調剤給付の管理会社が、この保険会社の調剤給付を行っていました。医療給付のヘルプラインに電話をすると、私の事前承認が通っていないため、調剤給付の管理会社に話を通さなくてはならない、と言われます。なので、今度は調剤給付の管理会社に電話をするのですが、この2つの薬は特殊な薬で、医療給付の管轄となるため、そちらのヘルプラインに電話するように、と言われます──ここは、つい先ほど電話したばかりです。事前承認の期限が切れると、内分泌内科で手紙を書いてもらわなくてはならないですし、医療給付と調剤給付のどちらのヘルプラインでも助けてもらえませんでした。最終的には、この状況を解決するため、会社の人事部から保険会社に連絡してもらいました。状況が変わるまでは、しばらく時間がかかりました。しかし、状況が変わったと言っても、保険会社は単純に、すでに通っている事前承認を延長しただけだったのです。こんなわけなので、数ヵ月後には再び事前承認が切れてしまうため、私は同じことを繰り返さなければなりませんでした。これには疲れ切ってしまいました。保険会社から見ると、私が死ぬのが一番であり、私と雇用主がカバーしてもらえるよう支払っていた保険の給付を拒否することで、そうなるようにしているのだと、この時、思ったのでした。それ以来ずっと、私はこの保険会社が嫌いです。
Chap1-10 放射線療法への挑戦
2005年1月、私は最終的に薬物療法を全てやめられるようになることを期待し、放射線療法を受けることにしました。「サイバーナイフ」と呼ばれる新しい手法で、より精密な放射線治療を行うことができる施設がサンアントニオにありました。海綿静脈洞が狭くてデリケートな作りであることを考えると、良い選択のように思えました。治療の準備としては、顔に着ける奇妙なマスクの作成と、MRIの造影検査がありました。マスクはたいしたこと無かったのですが、MRIでは、私の記憶が正しければ、「パワーインジェクター」という機械を使いました。あれは本当に酷かった! 検査の途中で技師さんが造影剤を注射するのではなく、検査の前に腕に点滴のチューブを入れられました。造影剤を入れるタイミングになると、この機械が私の血管の中に造影剤を物凄く速く入れてきたので、私は吐き気がして、気を失うか、そのまま死んでしまうのではないかと思いました。こんな感覚を味わったのは、後にも先にもこの時だけでしたが、この感覚は決して忘れないでしょう。およそ10分で回復しましたが、あれは本当に恐ろしかったです。私はもう二度と「パワーインジェクター」を自分に使ってほしくありません。「パワーインジェクター」などという専門用語は、人ではなく車に使うべきです。
放射線腫瘍科の先生は、治療チームと一緒に私の検査結果を確認すると、私に必要な線量を全て照射するには、特定の線量で3回行う必要があると判断なさいました。準備を開始してから1週間のうちに私は治療室に入り、治療台に横になり、自分の頭の型で作られたマスクを装着しました。巨大なロボットアームが私の周りをぐるぐると動き、様々な角度から頭に放射線を発射しました。それは、宇宙人に誘拐される人が出てくるSF映画のような感じでした。治療が終わると、頭の中の腫れを和らげるためにステロイドを処方されました。母と私は、翌々日に2回目の治療に来るつもりで帰宅しました。
放射線療法から回復するまでは酷いものでした。放射線で疲れ切ってしまい、ほとんど横になっていなければならなかったのですが、脳の腫れを和らげるために服用していたステロイドのせいで眠れませんでした。また、ステロイドのせいで気が狂ったように空腹にもなりました。腫瘍の手術の後にもステロイドを飲んでいて空腹を感じましたが、あの時はヒドロコドン配合薬も飲んでいたので、眠れない、ということはありませんでした。私は惨めでした。治療の翌日になると、放射線腫瘍科の先生に、2回目の治療には来ないように、と告げられました。機械の調整に懸念があり、放射線を予定よりも多く照射してしまったかもしれないというのです。3回目の治療については、翌日か翌々日中には知らせるとのこと。私は困惑し、腹が立ちました。もっと少ない線量だったら、こんなに辛くはなかったのでは? などと思いました。あまりにも調子が悪かったので、回復するまで本当に1週間のお休みで大丈夫なのか、と考えてしまいました。さらに1日が経過し、先生から電話がかかってきました。3回目の治療にも来ない方が良い、とおっしゃるのです。予定していた総投与線量には至っていないが、この時点では多過ぎる、とご説明なさいました。先生は、私が受けた線量でも充分に治療結果が出るので、それまで待ってみるのが一番良い、とお考えでした。こんなことがあり、確かに治療台にも、もう一度上がりたいとは思っていなかったので、気が動転し、苛立ち、最悪の気分にはなりましたが、この治療はもうやめることにしました。この話を聞いて、機械の調整がきちんとなされているかも確認せずに「出来損ない」の放射線治療を行った医師をどうして訴えないのか、と尋ねる人も何人かいました。その答えはとても単純です──私は軽薄な訴訟を良しとしていないからです。この医師と医療チームは私を助けようとしましたが、その過程でミスを犯したのです。このミスによって、数日間、私は不快でしたが、予定の総投与線量を超えたわけでもありませんし、彼らは取り返しのつかないことをしたわけでもありません。私は回復し、仕事に戻りました。医療訴訟とは、医師が犯したミスで、死亡したり、手足を失ったり、普通に生活して働く能力が損なわれたり、あるいは医療費が追加で発生してしまい、その分を保障してもらう必要が出てきたり、といったケースでのみ起こすものだ、と私は考えているのです。幸い、私の放射線療法はそういうケースではなかったので、そのまま前向きに自分の人生を歩んで行きたかっただけです。
放射線療法を受けてから5年以上が経過しましたが、その後も私のIGF-1の値には全く変化がありませんでした。放射線が何かをしてくれているとしたら、それは脳下垂体と海綿静脈洞に新しい腫瘍細胞ができるのを止めていることかと思います。あれ以来受けてきたMRIでも、瘢痕組織(はんこんそしき;傷跡を形成する組織)以外は何も確認されません。なので、もし放射線が、腫瘍が再度大きくなるのを防いでくれているのであれば、やる価値があったのだと思います。けれども悲しいことに、私には現在も薬物療法が必要です。放射線療法を受けようと思った元々の理由を考えると、これは期待外れの結果です。確か、サイバーナイフはガンマナイフほどの効果は無い、ということは何年か経ってから分かったことだったと思いますが、もしも、サイバーナイフではなくガンマナイフを選んでいたら、結果はどのように変わっていたか、と考えてしまいます。もっとも、そんなことは決して分からないでしょうけど。
Chap1-11 仲間とともに、希望とともに
2005年9月にダラス/フォートワースからサンアントニオに引っ越し、2007年10月にニューヨーク市内に引越し、そして2010年2月にはハドソンバレーに引っ越しました。近いうち、再びサンアントニオに戻るか、または他のどこかで新しい冒険を始めそうな予感です。これが私の生き方です。これが私のすることです。いつかは私もどこかに落ち着くとは思いますが、しかし今のところは、これが私の生き方なのです。新しい土地に行く際にはいつも、新しい雇用者が見つかるまでの間、COBRA(退職した後も、一定期間、辞めた職場で加入していた医療保険の契約を維持できる、という法律)を通して、確実に医療保険が使えるようにしていますし、仕事に就く際にも、頼りにできる良い保険が付与されていることを必ず確認するようにしています(どっちみち、保険は頼りにできるわけですから)。その土地で診てもらえる医師と、見つけられる限りで最高の内分泌内科医を確保して、その地に住むわけです。この医師たちが先端巨大症の実践的な知識を持っていなかったとしても、彼らが努力を惜しまないのなら、私は彼らとともに治療に取り組むことにしています。私の症例に興味を示さない医師を見つけたことはありません。「試合」のこの段階では、手術も放射線治療も受けてきたので、残っているのはIGF-1の検査と年に1回のMRI検査、それに薬の処方ぐらいです。私自身が、その時に行われている研究についてよく勉強し、試してみたい新しい治療法をチェックしていれば、ほとんどどんな医師とも治療に取り組むことができました。新しい治療法には期待を寄せています。私が診断されて以降、新しい薬も出ましたし、現在、埋め込み式の薬の治験が行われていることも知っているからです。希少疾病であることを考えると、8年間で大きな進歩です! 最初の手術、あるいは放射線療法のような大きな治療を受ける時は、生活や思考が病気に振り回されないようにするのは困難です──でも長い目でみれば、ほぼ普通に生活することができます。良い日もあるし、悪い日もあります。私の場合、疲れ切ってしまって寝なくてはならない日もありますし、他にも様々な症状があります。私はこういった症状は病気のせいであると分かっています。けれども、普通の日だってたくさんあり、とても気分が良い日だってあるのです。こういったことの、一つ一つに感謝しています。そして、なるべくこの病気に振り回されないようにし、確実に適応できる責任を持つようにしています──だって、そうしなくてはならないのですから。
また最近、インターネット上のコミュニティがだいぶ大きくなり、まとまった組織になったことに気付いたので、もう少し積極的に関わろうとしています。この病気を持つ人たちが、お互いや、新しく診断された人たちを支え合っていることには、とても驚いています。将来、もっと医療が進歩し、人々がより早くこの病気を見つけられるようになることで、診断までの長い道のりと、私たちの多くが受けなくてはならない治療から逃れられる日が来ることを願っています。今、これを読んでいる方は、新たに先端巨大症と診断された方か、あるいは、大切な人がそう診断された方かと思います。診断に導くこととなった苛立たしい症状や不可解なことを経験したり見たりしてきて、今、もしかすると本当に怖い治療に直面しているのかもしれません。人間として感じるあらゆる感情を経験していることかと思いますが、それは当然のことです。それでも、私の望みは、これからあなたが歩き出そうとしているこの旅では、ユーモアを忘れずに、希望を持ち続けてほしいということです。私たちの多くが同じことを経験し、それを乗り越えたということ、私たちはあなたの話し相手になれるということ、そして、世の中には絶えずこの病気の治療法を進歩させようとしている人々がいる、ということを覚えておいてください。8年が経った今も、私のIGF-1は落ち着いてくれませんが、それでもこれがいつも続くわけではないだろう、と希望を持っています。それに私には、やり場のない気持ちになり、あまり元気がない日があっても、私が体験していることを正確に理解してくれる友だちがネット上にいますもの。