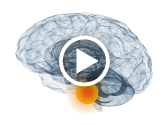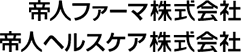ALONE IN MY UNIVERSE
独りぼっちの私〜先端巨大症との戦い
第3章
脳外科手術とともに歩む人生
マイケル・キャロル
第3章目次
- 第3章(1) はじめに
- 第3章(2) フットボールによる首の怪我
- 第3章(3) 突然の腕のしびれと妻のつわり
- 第3章(4) 手根管症候群が疑われる
- 第3章(5) 変形した椎間板
- 第3章(6) 先端巨大症と確定診断が下される
- 第3章(7) そして、最初の手術へ
- 第3章(8) テリーザの帝王切開とアメリアの誕生
- 第3章(9) いよいよ脳下垂体腫瘍摘出術へ
- 第3章(10) 脳下垂体腫瘍摘出術のその後-生きることの素晴らしさ
Chap3-1 はじめに
あらゆる物事には、不便なことがある。今ある不便さは感じても、未来の不便さについては見ることも感じることもできない。それ故、私たちは物事を改善せずして変化をもたらしてしまい、結果、悪い方向へ向かってしまうことが多い。
ベンジャミン・フランクリン
2008年は、私自身にとっても、私の家族にとっても、興味深い1年でした。私の母親は30年前の私の誕生を表現するために、「興味深い」という言葉を使います──多分それは、私が12ポンド(約5440g)以上の体重で生まれてきたためでしょう。2008年は、私が「先端巨大症」という病名と、この病気に関する様々なことを知った年でした。私は、病気が診断されるまでの道のりは人それぞれである、ということを学びましたが、私の経験も、それを証明するものとなります。その年、私には妊娠中の妻と幼い娘がおり、危険に晒された企業で仕事をしており、さらに大きな手術を2回受けました。そして、私は3つの重要な教訓を学びました。
1)フットボールによって命が救われることがあるということ
2)悪いことが起きても、実際にはすべてが悪いわけではないということ
3)恐怖には様々な側面があるということ
では、まずは記憶をたどっていくことにします。
Chap3-2 フットボールによる首の怪我
1994年、私は実家に居残った最後の子供でした。姉妹は結婚しており、そして2人の兄弟はすでに自分の仕事も家も持っていました。両親は50代で、フロリダに隠居する計画を綿密に立ててきました。ニューヨーク出身の私は、現役引退後にフロリダへ移住することは、実は州法によって定められているのでは、などと思っていました。
私は9歳の時、2人の兄弟の後を追ってフットボールを始めました。最初のコーチは私の父でした。初めの頃はフットボールが嫌いでしたが、最終的には大好きになりました。引越しが楽しみだったのは、フットボールが好きだったからでしょう。言ってみれば、フロリダのフットボールは、ティーンエージャーの少年にとって伝説なので、自分もそこに加わることを楽しみにしていました。どこの学校でも転校生であることはとても大変なのですが、フットボールチームに所属しているということは、とても良い会話のきっかけになります。私は早いうちからスターティングメンバーに登りつめ、スターティングガードとして活躍しました(私よりも上手くコーナーを守り、ダウンフィールドをブロックできるメンバーは誰もいませんでした)。さらに良いことに、チームはとても有利にスタートを切りました。
私たちの学校は、フロリダ州で同じ規模の学校の中でトップ5にランクインしており、それは非常に大きな成果でした。そういうこともあり、皆、とても真剣に練習に取り組んでいました。ある暖かな水曜日の午後の練習中(フロリダに他の季節があるのかは疑問ですが)、私はスターティングディフェンスに対抗する敵チーム役のオフェンスのランニングバックの代役を務めていました。その日の練習もいつものように進み、敵チーム役のオフェンスが健闘し、何点か得点もしました。そしてその時、事件は起きました。私は、右側に飛び込もうとして、ハンドオフ(味方に直接ボール手渡すプレー)でボールを受けました。しかし、あいにく私が走り込むべき隙間はなく、前方にまっすぐ進む以外、機敏に動き回りながら走ることはできませんでした。2人のディフェンダーが私の両足を片足ずつ抑え、視界の端に夜が訪れたかのような暗い影が見えました。しかし、私に向かってきたのは、不運にも280ポンド(約127㎏)のディフェンス・タックルでした。彼の頭がぶつかってきた時、一瞬目の前が真っ暗になりました! 私は地面に倒れた後、何度か目を覚まし、そして起き上がろうとしましたが、脚を動かすことができませんでした。倒れる前に、私は数フィートほど動きました。皆が私の周りに集まった時、私は「アイスクリームは?」なんて質問したことを覚えています。私は誰かがアイスクリームをくれるのでは? と思ったのですが、実際は誰もくれなかったことで少しイライラしました。深刻な首の怪我に苦しみつつも、私はフットボール選手らしく行動し、数分後には起き上がり、その場から「退場」したのです。トレーナーは、よくある脊椎ショック、またの名をスティンガー症候群(フットボールなどのコンタクトスポーツにおいて、タックルやブロックをした瞬間に首や肩、腕などに灼熱感を伴ったしびれをきたすこと)程度のものだろう、と判断しました。私の親はその日コーチと会い、コーチは両親に、私が脳震盪を起こしたことを話しました。しかし、そのことについて、誰もあまり深刻に受けとめませんでした。
翌朝、私は目を覚まし、学校へ行く準備をしていましたが、上下に燃えるような酷い感覚が脚と腕にありました。それを「針に刺されたようなピリピリした感覚」と言うのはあまりにも軽過ぎる表現です。「ナパーム弾に攻撃されたかのような感覚」と例えたほうが適切なくらいでした。それは前日に受けた神経外傷の後遺症でした。私が母と父にこの症状について話すと、彼らはすぐに神経科医に予約を入れました。予約枠はその日の午後まで空いていませんでしたが、それはそれで助かりました。なぜなら、その日はカトリックの男子生徒にとって重要な日であったためです──「指輪の式典」です。これは私にとって3つの大事なことを意味しました。
1)制服を着る必要はないということ
2)短縮日課であるということ
3)私は自分の指輪がまだ届いておらず、父の高校の指輪を受け取る予定だということ
私は非常に興奮していて、この日を逃したくはありませんでした。でも、残念ながら、運命は時々、ユーモアを使ったりします。私が学校まで車を運転していた時、車が故障しました。それで私は弱気になり、不安になり、時間に遅れながら、1986年式のプリムス・ダスターというハッチバック車をガソリンスタンドまで押して行きました。でも、ありがたいことに数人の同級生が私を見かけて、学校まで車に乗せてくれました。
その日はあっという間に過ぎ、指輪の式典が終わった後、父と母は私を医者のところに連れて行きました。神経内科医と神経外科医の所へ行くのはこれが初めてだったわけですが、その時、分かっていなかったのは、今後、ここに何度も来ることになるということでした。スンター先生は私に起きたことを注意深く聞くと、すぐに頚椎のMRIをオーダーしました。MRIは残念ながらレントゲン写真のように、すぐに結果が分かるものではありません。結果が出るまでの2週間は、実際にはもっと長く感じました。ようやく病院の受付から電話がかかってきた時、MRIの結果に何か異常があったようだというニュアンスで話をされました。そこで両親は、「もうフットボールができなくなったら、どうする?」という言葉を投げかけ、私に心の準備をさせようとしました。私は、勉強に集中するか、あるいは何か別のことを始める、などとボソボソ呟きましたが、実際はよく分かっていませんでした。もうフットボールができなくなるなんて考えられないことでしたから。
MRIの結果を聞く日が来ました。待っている間、非常に緊張しており、筋肉の一部がぴくぴくと震えてさえいました。スンター先生は部屋に入ってくると、MRIの結果が届いたことを私たちに告げました。先生は写真を貼り付けるディスプレイのライトをつけたのですが、すぐに消してしまいました。「正常な脊柱の模型を見てみましょう」。先生は模型を引っ張り出し、健康な脊柱の重要な部分をすべて見せてくださり、私がきちんと理解したかを確認されました。
「よし」と彼が言いました。「では、あなたの脊椎を見てみましょう」
「これは良くないに違いない」と私は思いました。私たちはディスプレイの所まで戻り、先生はライトをつけました。今度は健康な脊柱がどのように見えるかが分かっているので、私はすぐに問題に気付きました。スンター先生は私の首の3つの椎間板が突出していると説明しました。「テレンス(私にぶつかってきた少年)に感謝するべきか」と私は皮肉交じりに考えました。
その後、チームは私なしで進んでいきましたが、非公式ではあるものの、ある意味、私はコーチのアシスタントとして、オフェンス、特にオフェンシブラインの任務を果たしていました。あの頃の暗く辛い日々、バーニーコーチ(私たちはそう呼んでいました)は本当に私を助けてくれました。私が悪い知らせを聞いてからすぐ後にバーニーコーチがくれたグリーティングカードを私はまだ持っています。これはお見舞いのグリーティングカードだったのですが、内側にバーニーコーチが自分の言葉で、私のことを、そして苦難の時に見せた私の強さをとても誇りに思う、と書いてくれていました。私は大学で、この経験を題材とした小論文を書きました。人生で状況の変化に適応しなければならなくなった時について書くように、という課題が出たのです。やった! 場外ホームランが出たぞ! 私はフットボールから演劇クラブへ転身を遂げたのです。学業では素晴らしい成績を収め、日曜学校で子供たちにも教え始め、さらにパートタイムで働いて…他にも色々なことをしました。ストレスの多い状況に順応する私の能力はとても大きな財産だった、ということが、後に私が先端巨大症と診断された時に証明されると思います。
私は高校生の時に受けたフットボールでの怪我の治療に、多くの時間を費やしました。この本で主題となっているのは、とにかく先端巨大症なのですが、この診断に至るのはとてつもなく大変でした。先端巨大症は知らぬ間に進行する病気で、見かけ上は関連のなさそうな症状がいくつも出てきます。この病気によるダメージがたくさん出た後に診断されることが多いのです。私の場合は、診断の14年前に受けた首の怪我のおかげで、30歳で早期に診断を受けました。とても恵まれていたと思います。
Chap3-3 突然の腕のしびれと妻のつわり
2007年のクリスマスイブ、私はラスベガスに住んでいました。結婚して、マデレンという2歳の女の子がいて、妻のテリーザは私たちの2番目の子供を妊娠中でした。私の父と母は、なるべく私たちと共に過ごすようにしてくれる素晴らしい人たちなので、休日の間、私たちの家に滞在していました。クリスマスイブには父とゴルフに行くことにしました。ゴルフはフットボールでの怪我の後に始め、父と一緒に行くのが好きでした。その夜、私たちは伝統的なクリスマスイブのご馳走を楽しみました。妻、娘、そして母が台所で一緒に作業しているのを見て、胸が温かくなりました。マデレンが寝た後、テリーザと私はクリスマスで最も大切な仕事に取り掛かりました──娘のサンタクロースです。まず、マデレンが置いた2枚のクッキーを私が食べ、テリーザはニンジンを少し(彼女はほっそりした菜食主義者です)食べました。私たち2人がゆっくりとリビングをプレゼントでいっぱいにしている間、父と母はソファーに座っていました。プレゼントを並べ終えると、部屋の床が見えないほどになり、両親は私たちが正気ではないとでもいうように私たち2人を凝視していました。マデレンにとっては、これが何が起きたかを理解する最初のクリスマスであり、そして赤ちゃんがもう1人これから生まれてくることも相まって、このクリスマスはよりいっそう特別なものとなり、私たちはとてもわくわくしていたのです。
私は他の誰よりも早く、午前4時00分に目覚めました。いつもは早起きではないのですが、右手に非常に激しい痛みを感じ、眠っていられなかったのです。私は誰も起こしませんでした。痛みはいつ消えるのだろうか? などと考えながら、ずっとソファーに横になっていました。夜中に起きた時に、手のしびれに気づくことには慣れていましたが、いつもは手を振れば治まっていました。何年もこんな状態だったのです。けれども、あの日の感じは違っていました。しびれもありましたが、今まではなかった痛みが出てきたのです。そして、ようやく夜が明けた時、右手が腫れていることにも気付きました。私は型にはまった考え方をする人間なので、イブプロフェンを少し飲んで、その日をやり過ごしました。テリーザにもこのことについて話しましたが、「いつものように、すぐに治まるだろう」と思い、大げさには話しませんでした。とは言っても、頭のどこかで、首の怪我がいずれ悪い結果をもたらすことを知っていたので、ついにその時が来てしまったか、と思いました。でもクリスマスの日に、こんなことについてあれこれ思案したくなかったのです。
12月26日、痛みも良くならず、腫れも治まっていませんでした。私たちは皆、フットボールでの怪我が舞い戻ってきて、問題を起こしているのだ、と考え、テリーザと母が、「皆が医者にかかるべきだと言っている」と言いました。私はかかりつけ医のところへ行き、もう何年も前からの首の怪我について話しました。先生は、手首副子(手首を固定するもの)と抗炎症薬の他に、この症状が手根管症候群(※)と関係がある、と考え、神経学的な症状を減らす薬を処方してくれました。冬休みの10日間、これを試してみて、その後、必要があれば処方内容を調整することになりました。
冬休みが終わり、父と母も家に帰りました。例の不快感は改善されたものの、いまだに残っていましたので、もう一度同じ医師にかかりました。彼は敏感なので、私が「問題は手根管症候群よりも深刻なのでは?」と心配しているのが分かったのでしょう。先生は、まだ私が診察室にいる間に、神経内科医に電話をしました。神経内科医は炎症に対してステロイドを処方し、自分の病院のほうから私に電話をして予約を設定する、と私の医師に伝えました。私が帰ろうとした時、先生は私の肩をさすりました。私の不安を感じ取ったのだと思います。「心配しないでください。私たちがしっかりと治療しますから」と言いました。
病院を出て、処方せんの薬を出してもらうために薬局に行きました。処方せんを出した後、薬が出てくるのを待っている間、店の中をぶらぶら歩き回りました。5ドルのDVDをざっと見ながら、「自分の身体の問題は、本当は何なのか?」と考えました。手根管が原因であるとは信じられなかったのです。私はマデレンのために「フィッシュ・レース」というアニメを手に持って、調剤薬局の受付に戻りました。
処方された薬を飲んだ最初の日は、まるで20リットルのエネルギードリンクを点滴されたかの様でした。午前8時30分には、私はマデレンと一緒に公園におり、マデレンがよじ登ったものすべてに私もよじ登り、マデレンが四つん這いになってくぐったものすべてを私もくぐり、ブランコに乗ったマデレンを後ろから押し、そして、走ってマデレンを追いかけました。その後、私たちはごほうびを買うためにコンビニエンスストアに行きました──私たちは2人とも、スラッシュ(シロップ、氷、水を混ぜた鮮やかな飲み物)が好きなのです。私たちはお昼ご飯の時間帯に家に戻り、私は家を掃除し始めました。午後2時になるまでに、私は完璧に家をキレイにし、掃除機をかけ、トイレまで掃除していました。マデレンが昼寝をすると、私はスポーツジムに行きました。家に帰ってくると、どこかに夕食に出かけよう、と提案しました。頭がおかしくなってしまったのではないか、という目でテリーザは私を見ました。彼女は私に「いったい、いつになったら落ち着くの?」と尋ねましたが、ステロイドが私の静脈を勢いよく流れていたので、私自身にもよく分かりませんでした。その夜、眠れるかどうかも分からなかったのです。
ありがたいことに、ステロイドを飲み続けることで活動過剰な状態はおさまりました。翌週の終わりまでには、神経内科医との最初の予約診療に行っていました。その先生は親切で思いやりがありました。そして、他の先生からの紹介通り、どちらかと言うと強い訛りがありました。先生は私を見ると、スポーツ選手だった頃、何度も受けたことのある神経学的な試験を私に対して行いました。それから、MRIと神経伝導検査をオーダーし、再度ステロイドを処方しました。少なくともあと6日間、ものすごく活動的になってしまうことでしょう。
テリーザのつわりが始まったのは、ちょうどこの頃でした。テリーザは、アメリア(赤ちゃん第2号)の時のほうがマデレンの時よりもだいぶ調子が悪い状態でした。テリーザは大変で、マデレンを追いかけるようなエネルギーはなかったので、私は母に数週間の間こちらへ来てくれるように頼みました。いつもの通り母は非常に協力的で、翌日に飛行機に飛び乗ってきました。母はちょうど良い時にやって来ました。母が町に到着するやいなや、テリーザはある吐き気止めに対してひどい反応が出てしまい、それから数日、病院にいることになりました。
救急外来は混雑していたので、私たちは廊下の椅子に座るより他に何もできない状態でした。最初の看護師はテリーザのことを気にかけてくれた唯一のスタッフだったのですが、何時間かしたら帰ってしまいました。救急外来の医者は過重労働を強いられているので、私は彼らに多くは期待していませんでしたが、引き継いだ看護師は、看護師という仕事を好きそうには見えませんでした。私とその看護師は、彼女の意見を聞くためではなく医師の診察を受けるためにこの場にいる、という事実について意見の相違が生じてしまい、強い言葉で言い合う瞬間がありました。私はテリーザをベッドに寝かせて様子を観察すれば、呼吸状態も良くなるのでは、と感じましたが、この看護師とは意見が合いませんでした。テリーザの産科医は私の意見に同調してくれましたので、私が勝ったのだと思います。しかし、テリーザが唾液を普通に飲み込めず、腫れた唇から唾液が流れ出てしまい、それを押さえるために自分で口にタオルを当てているのを見ていたら、とても勝ったような心地はしませんでした。真夜中、テリーザは私の誕生日を祝ってくれました。それは30歳になるという、私にとっては重大な出来事だったわけですが、とんでもないスタートとなってしまいました。
テリーザは、私の誕生日の夕方にようやく病院から解放されました。私たちは車に乗り、家に帰りました。ドアを開けて家の中に入った時、黒い風船と枯れた花が私たちをお出迎えしました。私の母が、私の誕生日を祝って精一杯頑張ってくれたのです。母とテリーザは、それまで数日にわたってこれを計画していました:私が兄の30歳の誕生日に、兄の職場へ葬儀の手配を送ったのが始まりで、これは家族の中では慣例になっていました。私たちは皆でしばらくぶりに笑いました。その後、数日でテリーザは調子が良くなり、元気も出てきたので、母は家路につきました。
Chap3-4 手根管症候群が疑われる
母が帰った週の土曜日、神経伝導検査のために、私たちは皆で神経科へ行きました。これは、手根管症候群の可能性がある患者を拷問にかける、という考えの基だけに開発されたような検査でした。腕の中に電気を流す電極と筋肉に刺さっている針がある状態で、特に楽しいものは何もありません。この検査の目的は、神経伝導のスピードを測ることです。手根管症候群だと、信号が神経の端に届くまでに通常よりも長くかかります。実際のところは、私は手根管症候群の方がまだ良い、と思っていました。もうひとつの可能性は首の怪我によるものであり、そうだとしたら手術が必要なのではないか、とかなり確信していたからです。
私は指示通り、MRI検査も受けに行きました。出会ってからしばらく経ちますが、親しい旧友である磁気共鳴断層撮影装置は進化していました! 今回のMRIには、頭を入れるためのケージがありました。1994年にはなかったものです。さらにMRIの技師さんは私にヘッドホンを渡し、私のために衛星ラジオをかけてくれました。再度言いますが、ずっと以前にはなかった贅沢です。こういう小さなことは楽しむべきですよね? あなたが閉所恐怖症ではない限り、MRIは楽しいひと時です。ありがたいことに、私は閉所恐怖症ではありません。私はかなり肩幅が広いため、機械の中にかろうじて入ることができました。また、頭も鼻もかなり大きく、4人の家族が雨宿りできるぐらいなので、私の鼻の頭は機械に触れそうでした。実際、私の鼻は大きくなっているようでした。このことについてはあまり考えたことがありませんでしたが、後になって重要になってきました。かつてないほど最悪なドラムのソロが30分続いた後、私は機械から引き出されて、家に帰されました。
私の最初の怪我の後に忘れていたことのひとつに、待つということは怪我をするのと同じぐらいつらい、ということがあります。いつもうんざりしてしまいます。今回は、首が良くなるのを待っているような状況からは、程遠い気分でした。私の恐れは「これがどれぐらいつらいことになるのか?」ということでした。首の椎間板が、M-80(爆竹)を落とされたクラゲのように爆発する光景が思い浮かんだのです。すべての椎間板が手術で融合され、永遠に頭を動かすことができなくなり、ただ真正面を見ている状態を想像しました。もうドライブしたり、見上げたりすることができなくなるのではないか、と。何もしてもらえず放置されている時、心は自分に酷いことをします。その上、私の勤める会社が、重大な金銭問題を抱えているという噂も聞きました。すべてのタイミングは完ぺきでした。自分の首の問題がある中、妻は私たちの2人目の子供を妊娠しており、最も近い家族は2,500マイル離れたところにいる、という状況に置かれ、私は不確実な未来に直面していました。