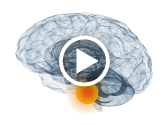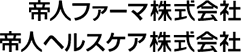ALONE IN MY UNIVERSE
独りぼっちの私〜先端巨大症との戦い
第2章
先端巨大症恐怖症
マイケル・クックマン
“You can conquer almost any fear if you will only make up your mind to do so. For remember, fear doesn’t exist anywhere except in the mind.”
「決心さえすれば、どんな恐怖も克服できる。覚えておけ、恐れは心の中にしか存在しないのだ」
デール・カーネギー
耳がおかしくて医師にかかる場合、普通は「たいしたことはありません。すぐに良くなりますよ」と言われることを想像するかと思う。だから、 例えば「脳に腫瘍がある」なんて言われるとは思いもよらないだろう。ところが、僕が、子どもの頃以来、初めて家庭医(一般開業医)にかかった時、本当にこんなことが起きたのだった。
右耳が少し聞こえにくくなっていて、左耳と同じようには聞こえなくなっていた。それで、職場で入っている保険で診てもらえる5人の医師のうちの1人に診療予約を取った(注:アメリカの医療保険の中には、かかりつけの家庭医や一般開業医の選択肢が限られているものがある)。僕はそれまで一度も医師を選ばなくてはならない状況に直面したことがなかったので、単に家から近ければどんな医師でもかまわない、としか考えていなかった。
聴力のことで診察してもらったのはC医師である。
C医師の診療所はイリノイ州エバンストンのセントフランシス病院にあった。そこは僕が住んでいた所から、「Lトレイン」という電車で数駅しかなく、そう遠くなかったし、駅から病院、そして先生の診療所までは、良い散歩になった。受付では書類を記入しなくてはならなかったが、その後はほんの数分で診察室に呼ばれた。先生に聴力のことを話すと、先生は僕に、「“アクロメガリー(先端巨大症)”って、聞いたことありますか?」と尋ねた。
「“アクロメガリー”? いえ、一度も聞いたことがありません。新しいロックバンドですか?」
大笑いして床に倒れ込んでくれるかと思っていたが、期待外れな結果となってしまった。その代わり、先生は笑顔でこう言った。「いえ、違います。脳下垂体が成長ホルモンをたくさん作り過ぎてしまう病気です」
ああ、あまりたいしたことではないな、と僕は思った。「成長ホルモンがたくさん」といっても、それほど酷いことではないだろう、と。治療薬があるのかどうかを尋ねると、先生は「まあ、あるにはありますけどね」と言った。
この先生の言い方で、僕は、「これはちゃんと考えたほうが良いことなのかもしれない」と思った。先生は僕の耳を掃除すると、今度は院内の別の場所で脳のMRIを撮るように勧めてきた(脳は脳下垂体がある場所である)。そんなことで、僕は次の週に予約をとった。
僕は10年以上勤めている書店へ仕事に行き、週に1度、シカゴのノースサイド、ロジャーズパークの自宅から1ブロック離れた所にあるコーヒーショップでマジックショーを行いながら、いつも通り過ごしていた。コーヒーショップは僕がガールフレンドのサルに出会った場所でもある(ガールフレンド? レディーフレンド? あなたが40歳だったら何と呼ぶかな? 僕はガールフレンドと呼ぶことにするよ。もし気になるようなら、他の呼び方に置き換えて読んでほしい)。僕たちは2人ともこのコーヒーショップの常連で、運命的に出会ったのだが、この辺のことについて少し整理して話したいと思う。さて……。
実際には僕の生活は単調になってしまっていたため、変化を求めていた。書店で働き、家に帰って読書をしたり、同僚など付き合いのある人達と飲み行ったりするだけの日常とは何か違うことがしたかったのだ。確かに、市内の小学校でマジックショーを行うこともたまにあり、練習もたくさんしたのだが、それだって定期的なスケジュールとして見なすほどのものではなかった。
僕が何を探していたのか、自分でも分からない。人生の転機が訪れようとしていても、僕は気付かなかった。
脳下垂体がおかしいことは分かっていたが、脳下垂体とは何かが分からないうえに、どこにあるかも知らなかったから、これが深刻なことだとは考えていなかった。確かに脳下垂体について聞いたことはあったが、扁桃腺のようなものだと思い込んでいた。何かあれば切り取って、あとはいつも通り過ごせるものだと、そんなふうに考えていた。
病院には予約の30分ぐらい前に着いた。待っている人がたくさんいると思っていたし、書類も記入させられると分かっていたからだ。何事であれ、前もって行動するのが一番だ。しかし驚いたことに、コンピューターとファイルがたくさん置いてあるデスクの向こう側に素敵な女性がいるだけで、他には誰もいなかった。彼女はすでに僕が誰なのかを知っており、記入用紙を僕に手渡すと、「すぐにお呼びいたします」と言った。彼女のタイプライターをちらっと見ると、その紙には僕の名前と「脳腫瘍の疑い」という文字が見えた──深刻な事態であることを知った瞬間だった。事の重大さを知ってそのまま気を失う可能性もあったため、彼女が僕に座っているように言ってくれたのは幸いだった。足からは間違いなく力が抜けていった。僕は書類に記入しながら、自分は間違った書類を見たのだろう、あれはきっと他の人のものに違いない、と考えて落ち着こうとした。しかし、彼女から書類を渡された時、悪夢は現実のものとなった。
僕はMRI検査を行うためにそこにいたわけだが、その時はMRIが何であるのかということすら知らなかった。後になって、MRIとは「磁気共鳴映像法(magnetic resonance imaging)」であることを知るのだが、頭文字よりもフルネームのほうがかっこいいと思っている。先ほどの素敵な女性が僕をロッカーのある部屋へ案内してくれた。僕は病院のガウンに着替え、すべての物、特に鍵や、その他、磁気を帯びた物をロッカーの中にしまわなくてはならなかった。あの時、ずっと頭の中で「なんだかとんでもないことに巻き込まれてしまったなあ」と考えていた。MRI検査についてだが、簡単に言えばこんな感じだ──患者が横になるためのベルトコンベヤーの付いた、大きくて恐ろしい機械の中に入るのだが、この機械は騒々しい音を出すので、耳栓をしなくてはならない。そして、機械に対して後ろ向きに乗っかって機械の中に入ると、突然、自分の体から壁までが5㎝ほどしかない世界になる。皆のご機嫌を損ねないように、体を動かさないようにしなくてはならない。皆を喜ばせるために、僕はとても恐ろしい思いをしなくてはならなかった。
自分がブリキ缶の中にいるとすると、誰かがその中に入ろうとしているかのような、カーンカーンという金属音がしばらく鳴るのだが、2~3分でこの音が止まる。さらに2~3分経つと、再び音が鳴り、これは30分ぐらい続く。それが終わると、ベルトコンベヤーは丁寧に患者を機械の外に出してくれる。この時、再び動けるようになることを、この上なく嬉しく感じることだろう。そして、自分の服を着て家に帰れるなんて、まさしくボーナスといったところだ。
職場では、「これは念のために調べているだけ。心配しないで。きっと大丈夫だから」と皆に言われた。彼らは親切だったが、僕は「脳に腫瘍があるかもしれない」と思い悩んでいたため、思いやりある人たちの「大丈夫ですよ」という言葉は、ほとんど耳に入ってこなかった。
MRIの結果はおよそ1週間で分かるとのことだったが、C医師から電話をもらうまでは100万年ほどにも感じられた。先生は、僕には確かに脳腫瘍があり、何かしらの治療が必要である、と言ったので、治療の選択肢について説明を受けるため、僕は先生に会いに行った。シカゴのLトレインの駅から家々やアパートの建ち並ぶ通りを歩くのは心地よいはずなのだが、静かで心地よい秋の朝に、僕は不安を胸に病院に向かってとぼとぼと歩いていた。
腫瘍? いったい何のことだよ? なんでそんなものがあるんだよ? 発作を起こしたりしないよな? 僕は消えてしまうのかい? これからも、まだ虹の色を見ることはできるのかな? なぜナルコレプシー(強い眠気の発作を生じさせる脳の病気)ではなかったんだろう? ナルコレプシーだったら、少なくとも眠ることができただろうに。
診療所で、C医師は僕に、この腫瘍は成長ホルモンを過剰に分泌していて、そのせいで僕の額と顎がかなり出っ張っているのだ、と説明した。額と顎については、僕自身、気付いていなかったが、先生は気付いていたのだ。先生は僕に、長年の間に何か気付いた変化は無かったか、と尋ねてきた。昔とは違って、僕の手の指の関節はなんとなく大きくなっていて、歯は奇妙にことなっていた──歯と歯がなんとなく離れていたのだ。そして明らかに、話すのにも支障をきたしていた。だが、歳を重ねれば誰にでも起きることだと思っていたし、それに、自分はごく普通で、奇妙な病気にかかる類の人間ではないと思っていた。
しかし、実際そうなったわけだから、僕は間違っていたのだ。こういった変化はすべて先端巨大症の徴候であり、脳にある腫瘍によるものだった。この腫瘍は、足や腕ではなく、脳にあったのだ。
C先生は先端巨大症の手術をする外科医との予約を設定してくれたのだが、珍しい病気であるため、僕は、その外科医にはこの種の手術の経験がどれだけあるのだろう、と考えた。しかし、自分では手術できないことは明らかなので、あまりごちゃごちゃ考えないようにした。
外科医のイニシャルも同じくCなので、紛らわしくならないように彼をCt医師と呼ぶことにする。この先生の診療所は少し遠く、シカゴ市から少し離れたスコーキーにあった。診療所に入っていくと、そこは、僕が家を出た時から思い描いていたとおりの場所だった。ここも、他の医師の所と同じような感じだった。小さな待合室では3~4人の患者さんが雑誌を読んだり、床を見つめたりして、お互いを見ないようにしていた。「これは誰かが僕に仕組んだ、手の込んだとんでもないジョークなのでは?」などと少し思いを巡らせていると、スタッフがやって来て、僕を診察室に通し、「すぐに先生が来ますからね」と言った。
まもなくCt医師が入ってきたが、僕は最初、彼を診察の前段階での問診を担当する若い実習生かと思っていた。ところが、この人こそがCt医師ご本人だったのだ。先生は、きちんとカットした短い茶色の髪をしており、 「ゆかいなブレディー家」(ホームコメディー)にいかにも出てきそうな顔をしていて、12歳くらいに見えた。先生は僕のMRIの写真(レントゲンか何か)を貼ると、腫瘍について話し出した。
僕に理解できたのは、腫瘍があるということ、その腫瘍を取らなくてはならないということ、すぐに取らなければ、盲目になったり、体の様々な機能を失ってしまったり、本来の寿命よりも早く死んでしまう、ということだった。この、最後の表現については、はっきりとは理解できない。本来の寿命など、いったい誰が知り得るというのだろうか? 明日、車にひかれて死んだとしても、それが本来の寿命よりも前だったと言えるのだろうか? もしかすると、本来の寿命よりも後かもしれないし……。あるいは、本来の寿命などというものは無く、いつでも好きな時に死ねるのかもしれない。とにもかくにも、僕はこれが深刻な事態であると理解し、僕はこの日から2週間以内に手術を受けることに同意した。不安に怯え、自分を憐れむのには、2週間で十分だった。
手が少し変形していたり、こめかみの辺りで頭の大きさが変わっていたりしていたのは、すべて、脳の中にあるこの腫瘍(それが何なのかはともかくとして)のせいだったのだ。腫瘍なんて出来てほしくなかった。僕はこれまでほとんど病気をしたことがなかったのだ。実際、大変な病気をしたのは、子供の頃にかかった気管支炎ぐらいだが、これだって2~3日学校を休んだだけで済んだ。母はあの時、とても心配していたが、僕はすぐに何事も無かったかのように回復したのだった。
しかし、この“アクロメガリー(先端巨大症)”は……。なんてこった。この病名を言えるようにするだけでも、しばらくかかった。この病気について、自分でもよく分からない状態で誰かに説明するのを想像してみてほしい。善意ある友人たちは、無意識のうちに、突然、専門家のようになってしまい、「医者は間違っている。脳下垂体腫瘍などというものは無い」とか「こうであるなら、そうでしょう」「そうであるなら、こうでしょう」などと言うようになる。だが、僕は医師に身を任せることにした。医師も僕を助けようとしていたし、彼らには自身の意見を裏付ける医学的根拠もあったからだ。
手術は月曜日の午前に予定された。その前日の日曜日、僕は怯えながら、ほとんど1日、ひとりで家にいた。手術が失敗して、眼が覚めた時には失明しているかもしれないし、さらに失敗すれば眼が覚めたら死んでいた、なんていうことになるかもしれないし、そんなことになれば、僕は塞ぎ込んでしまう。あるいは、手術がうまくいって治るかもしれない。いずれにしても、僕の脳には腫瘍があるわけだが、脳にそんな物は出来てほしくなかったし、もっと言えば、体のどこにも出来てほしくなかった。ここで初めて、僕は死すべき運命について考え、「次のクリスマスとかの祝日には、この世にいないかも」「兄弟姉妹や従兄弟たちには再び会えないかも」などと考え続けた。
こんなふうに考えるのが嫌だったので、僕はギターと毛布を手に取り、湖に向かった。芝生の上に座り、しばらくの間、ギターを弾いていたのだが、突然、雲が空を覆い、雨が降り始めた。「僕が少しメロドラマ風になりすぎたからこうなったのかな」なんて思いながら家に戻った。
月曜日の朝4時は暗く、家の近くのLトレインの駅まで歩いた時、稲光が空だけではなく建物や歩道、そして僕の目の中など、いたる所でぴかっと光るので、外科医にやられる前にこの天気にやられそうだな、と思った。そして、この考えに思わず自分でも笑ってしまった。笑ったら気分が良くなり、僕はここしばらく、笑っていなかったことに気付いた。せっかくの笑顔を無駄にしたくなかったので、自分の笑顔を見ようとした。稲光に合わせてお店のショーウィンドウを見たので、自分の笑顔がとてもよく見えた。すると、歯を磨いてこなかったことを思い出した。僕は、病院のスタッフがそれを気にしないことを願った。
Lトレインはガラガラに空いていた。他の乗客は前の座席に頭をあてて眠っており、空席だらけだった。だが、僕は座らなかった。たった3駅だし、それに少し緊張していたからだ。電車は僕の下りるサウス・ブールバードに停車した。病院まで4ブロック歩いたとき、何度も稲光が周囲を明るく照らし出した。僕は再び怖くなってしまった。
僕の病室はごく小さく、ベッドは1つしかなかった。2人の小柄で若い看護実習生に、ベッドに横になるように言われ、何か必要なものはないか尋ねられた。この2人はとても陽気で、やる気満々だった。僕が、「その元気を分けてほしいです」と言うと、2人は笑いながら(僕にはそう見えた)、「そうできるなら、そうしたいぐらいです」と言った。2人がいなくなると、僕は2~3分ほど1人になった。すると今度は、ボディビルダーのように大柄なスタッフがやって来て、「これから手術室に行きますよ」と言い、ベッドの金属製の柵を掴んで、ドアの方へ向かって僕を載せたベッドをぐいっと引っ張った。僕はとにかく彼に殴られないことを願った。でも、今は病院にいるわけだから、殴られようが何をされようが、大差ないか……。
僕は、広くて長い廊下の両側で、聖歌隊が讃美歌を歌う中、手術室へ運ばれて行くのを想像していた。すると、高さがかなりある大きなドアが開き、観衆は患者の登場に拍手喝采。ホルンが壮大なメロディーを奏で、少女たちがダンスをしながら「手術室へようこそ」と歌う。……悲しいかな、現実はそうではなかった。先ほどのスタッフは、僕を3メートルほど引きずって廊下を横切ると、ベッドでドアを押し開けた。中には、ごく数名の医師が立っており、そのうちの1人は僕が2週間ほど前に会った、例の12歳小僧だった。
「やあ!」と彼が言った。「調子はどうだい?」
どのように答えるべきか分からず、それで僕はただ「悪くはないです」と言った。
「そうこなくっちゃね!」
すると、そんなに陽気ではない感じの人が、自分は麻酔科医であると自己紹介し、「全然痛くないですよ」と言った。そして気が付くと手術は終わっていた。どうやらうまくいったようだ。手術とは、こんな感じに運ぶものなのだろう。「うまくいかないのではないか」と思っていると、次の瞬間には意識が無くなっている、でも自分では意識が無いなんて分からない。これ、分かるかな?
目を覚ました時は物凄く意識が朦朧としていたし、本当に何が起こっているのか分からなかった。目は見えたのだが、話せるようになるのには数秒かかったため、怖くなった。緑色の手術着を着た人達が流し台の所にたくさん立っていて、道具と思われるものを洗っているのが見えた。僕はうっかり、「いったい何が起きているっていうんだよ!」と言ってしまった。看護師の1人が僕をちらっと見て、「今、麻酔から覚めてきているのよ」と言った。明らかに、「まったく、赤ちゃんなんだから」といった口調だった。
次に気付いた時は夜で、僕は集中治療室と呼ばれる、これまた奇妙な場所にいた。ここにいるという事実や、どうしてここにいるのかということを思っただけで、ちょっと怖くなった。でも、周りには看護師がたくさんいたし、医師も時々ぶらりとやって来ては、指示を出していた。
どういうわけか、集中治療室の照明は少し暗くなっていた。おそらく、こうやって恐怖心を煽ろうとしているのだろう。頭の左側から5㎝ぐらいのところに小さなテレビがあり、僕は眠りに落ちるまで映画を見ていた。他に何もやることがない時はこれが一番だ。
翌日、僕は通常の病室にいた。ここには窓も電気も電話もあった。ドアを出てすぐ近くには受付があり、いたるところに人がたくさんいた。気分は上向きになり、少し安心した。外は晴れており、未来は明るく見えた。集中治療室から他の病室に移動した時の記憶は全然ない。看護師によると、麻酔の効果は数時間残ってしまうものだそうで、その影響で覚えていないのでは、とのこと。おかしなことに、覚えていることと、覚えていないことがあるんだけどね。まあ、いいか。
その朝、それまで会ったことのない医師が部屋にやって来て、ベッドの上に薬の入った瓶を2~3本放り投げ、「これを飲んでね。飲まないとだめだよ」と言って出て行った。
入院中、C医師の診療所から皆が見舞いにきてくれた。皆、僕の手術について心配しており、C医師によれば、診療所では皆が僕のことばかり話している、ということだった。こんなことを言われたので、僕は有名人になった気分だった。とは言っても、病院のベッドにいて、鼻にはガーゼが入っていたし、カテーテルにも繋がれていたわけだが……。鼻の中にガーゼが入っていた理由は、外科医が鼻から脳の手術をしたからで、脳に入っていく途中、邪魔な物を脇に押しやって……ああ、気にしないで。まあ、分かるよね。
テレビで「ギリガン君SOS」(コメディードラマ)を3日間見た後、タクシーで家に帰された。
外科医は、手術はうまくいった、と言い、薬を放り投げてきた例の医師も同じことを言っていた。ちなみに、この時の薬は、甲状腺の機能を正常に保ち、血圧を下げるためのものだったらしい。これで間違いなく、「僕は大丈夫だ」と思えたので、2週間後には仕事に戻った。皆は、少なくとも僕に会えて嬉しがっているように振舞っていた。面白いことに、脳の手術をしたと言うと、必ず好奇の目で頭を見られる。おそらく、まだ脳みそがきちんとあるのか知りたいのだろう。
日常を取り戻し、こういったことが全て過去のこととなって良かった。しかし2週間後、外科医から電話がかかってきて、また手術をしなくてはならない、と伝えられた。
もう1度、手術をしなくてはならない……。どうやら1回だけでは十分ではなかったようだ。彼らは、1回目は真剣にやらなかったということだろうか? なんだかんだ言ったって、これは脳外科手術だぞ。彼らがふざけていたとは思わないが、それも分からない。僕は医者ではないし。ちくしょう! 「私は医者ではありませんが、テレビでは医者を演じています」なんていうコマーシャルがあるが、僕なんてテレビで医者を演じてすらいない。
この少年ドクターとの会話は次のような感じだった。
僕:「どうして、また手術が必要なんですか?」
先生:「腫瘍を全部取れなかったからです」
僕:「どうしてです?」
先生:「視神経に近すぎたからです」
僕:「あのう、今だって視神経に近すぎるんじゃないですか?」
先生:「そうですが、今回はもっと積極的に攻めるつもりです」
僕:「たった2週間前のことですよ。あの時に積極的に攻めれば良かったじゃないですか?」
先生:「そうですが、視神経に近すぎて……」
はいはいはい。手術や脳腫瘍などの、先端巨大症に関するものについて、僕は何も理解していないことは認めなくてはならないが、それにしてもこれはおかしいと思った。C医師に相談すると、同意してくれた。C医師は、この分野では世界的にも有名な別の外科医に僕を紹介してくれた。この外科医の名前も同じくCで始まるので、彼のことはC Note医師と呼ぶことにしよう(注:米国では、“C Note”という言葉には、「100ドル紙幣」という意味がある)。
C Note先生のほうがしっくりくる感じだった。年齢を重ねており、経験豊富で、穏やかで気さくな人だった。それに、この先生は「逃亡者」でジェラード警部を演じたバリー・モースという俳優に似ていたので、これは最高だ、と思った。
Ct医師は、クリスマスの頃に2回目の手術の件で電話をかけてきた。僕は彼に少し考えさせて欲しいと言った。最終的に、翌年4月にC Note先生に手術をしてもらうことに同意した。手術までの長い期間、僕は自分の健康と将来について心配していた。体の中にあるのは、風邪でもウイルスでも肺炎でなく、脳腫瘍なのだ。脳の中に腫瘍だぞ。なんてこった!
僕のまあまあ普通の生活は、ここ数ヵ月のうちに、なんだかよく分からないものになってしまった。病気であることすら知らなかったのに、ある日……ええと、手ではなく、足でもなく、脳に腫瘍があることが発覚したのだから。
ある朝、僕は大好きな地元のコーヒーショップに行ったら、とても混んでいた。食器や色々な器械の音でうるさかったはずなのに、僕が空想の世界から解き放たれることはなかった。僕は母のことを考えていた。母は、僕が診断を下される前の12月に他界してしまった。それまでは、祝日に実家にこっそり戻って母を驚かせようと思っていたのだ。けれども、母は突然この世を去ってしまったので、結局、この計画は実現しなかった。僕は泣き出してしまった。公共の場ということもあり、泣きたくなかったが、どうすることもできなかった。
僕はコーヒーカップを置くと、壁の方を向いた。小さな女の子がお母さんと一緒に注文したものを待って立っていた。女の子はお母さんに、なぜあの男の人は泣いているのかと尋ねていた。お母さんは分からないと答えた。この子は僕の方に歩いてきて、僕を見た。
「ねえ、おじしゃん、」と話しかけてきた。「泣かないれね」そして小さな手で僕の頭をぽんぽんと軽くたたいた。当然、僕はもっと泣いてしまった。
2回目の手術だが、手術中は意識が無かったから自分の目で見たわけではないが、1回目よりもずっと上手くいった。1回目の時よりも、話しにきてくれた医師も多かった。残っていた腫瘍を取ったけれども、頸動脈に非常に近くて危険だったため(頸動脈はいじくりまわさないほうが良い)、全部は取りきれていない、と聞かされた。腫瘍と一緒に脳下垂体もかなりの部分が取り除かれてしまったため、薬が必要になった。
C医師がノースウェスタン・メディカルに僕を紹介したため、ろくでもない大都会、ループエリア(シカゴのビジネスの中心となるオフィス街)に今までより頻繁に行くことになってしまった。今度はCではないイニシャルのM医師という内分泌科医が僕の担当になった。先生は、脳下垂体の働きを補う注射を処方した。僕はこの注射を6ヵ月に1度打っていたが、1番の問題はあいかわらず成長ホルモンだった。
この注射を打っても、特に変化は感じなかったが、効果は出ているようだった。保険のおかげで、自己負担は1ヵ月あたり35ドルだった。できればこんな金額、支払いたくなかったが、まぁ、仕方ない。注射で少しでも長生きできるのなら、これも悪くないだろう。
1年ぐらいすると、1ヵ月あたり3,000ドルも請求されるようになった。こんな金額、絶対に払いたくなかったので、すべて、つまり医者や薬から離れていった。
僕が前述のガールフレンド、サルに出会ったのは手術のすぐ後だった。シカゴのノースサイドにあるメトロポリス・カフェで出会ったのがきっかけだった。ある夜、僕はトランプの手品を練習しており、サルは入口の近くにあるソファーに座っていた。彼女は僕の方へやって来て、テーブルを挟んで僕の真向かいに座り、「さて、何か見せてちょうだい」と言った。
「何か」とは手品のことだと思ったから、僕は手品をした。このコーヒーショップで、僕は以前にも何度か彼女が他の人たちと話しているのを見かけたことがあった。彼女の長いブロンドの髪や、話す時の笑顔が好きだった。笑うと口元がちょっと歪んだ感じになるのだが、それが彼女の美しさを引き立てていた。
サルは学校の先生で、8年生(日本では中学校2年生)に代数学を教えており、今も現役だ。彼女は、僕が書店で働きながらセミプロの手品師をしていることに好感を持ってくれた。僕たちはその夜、お互いについて色々語り合い、しまいには、彼女のルームメイトで大親友のジェニーにも会った。嬉しいことに、彼女たちは僕の家からわずか数ブロックのところに住んでいた。
月日が過ぎても、僕は先端巨大症についてサルに話す気にはなれなかった。本当にどうしてなのか分からない。一緒に過ごすことが多かったので、病気を隠すのは難しかった。
1つだけ確実なことがある。数年の間、薬を使わずにいたら、頭がとてもぼんやりとしてきたことだ。職場にいる時やサルと一緒の時、外でバランスを崩して倒れてしまうことがあった。そんなこともあり、病気についてサルに全て話すのは、今が良い時期だと思った。
ある晩、家に帰る前にメトロポリス・カフェに立ち寄った時、僕は彼女に自分の病気について話をした。彼女の反応は僕の想像とは異なっていた。
「注射をやめるなんて、なんでそんなばかなことを?」いつものテーブルで、僕の真向かいに座った彼女が尋ねた。
「あまりにも高かったから」
「でも、それだって会社がどうにかしたわけでしょ。いったいぜんたい、どうなっているのよ?」
初めて彼女に手術も含めて全てを話した時、彼女は静かに座っていたが、目を丸くし、口は開いていて、顔には質問がたくさん浮かんでいた。
ある夜、僕は図書館から歩いて家に戻ろうとしていたら、めまいがして歩道に倒れ、頭を強く打ってしまった。血が流れて目の中に入り、頭痛もしてきた。それでも、家からたった2ブロックのところだったので、家に向かって歩いていった。すると、サルが家の前の歩道に立っていた。僕を見て怖がっているようだった。ジェニーを誕生日祝いに飲みに連れて行く予定を入れていたことを、僕が忘れてしまったのかと思い、確かめに来ていたのだ。
彼女は浴室で僕をきれいにすると、「今夜は家にいて。ジェニーも分かってくれるわ」と言った。誰かが気にかけてくれるのは、ありがたいことだ。
それなのに僕はしくじった。僕はいつだってしくじるのだが、今回はしくじりたくなかった。でも、しくじってしまったのだ。
ある夜、一緒にテレビを見ている時、サルが職場のことを話していた。僕は彼女の言っていることがよく理解できなかった。すると、例の症状が現れた。
サルは僕の顔の前に自分の顔を持ってきて、「あなたの心はいったいどこ?!」と叫んだ。
彼女は、僕がかなり長いことよそよそしくしていたと言い、これは僕がもう彼女のことを好きではないからだ、と解釈した。彼女が「これで終わりよ!」と言って、ハンドバッグを手にして立ち去った時、僕はもう少しで泣き出すところだった(僕は泣き虫だが、それが何か?)。
10階の部屋から外を見ると、サルは道を渡っているところだった。彼女がX脚気味に可愛らしく歩くのを見るのがずっと好きだったが、今回は、彼女は立ち去っているのだった。僕は、今までの自分の失敗について考えた。子どもの頃から、いつも人に怒鳴られてきたし、父にはいつも、お前はろくな人間にならないと言われてきた。僕は何もかも失敗してしまうのだ。サルが去っていくのを、僕は立って見ていた。今回は、帰宅や出勤のために去っていくのではない、今回は僕から去っていったのだ。この夜のことを思いだすと、いまだに涙がこみ上げてしまう。
ある日、M医師からメールが来た。新薬の治験に参加しないか、という内容だった。これは僕がすでに使用している薬と似た薬だった。僕は再び健康な状態を取り戻さなくてはならなかったので、この勧めに応じることにした。僕はいつもふらふらで、脚と肩は1日中痛んでいた。それに、仕事もうまくいっていなかった。サルが去った後、テレビを見る以外は特に何もしていなかったため、この生活スタイルを変えたいと思っていた。倒れて大怪我をしたり、脳卒中や心臓発作を起こしたり、怪物に仕留められたり、とにかく何か良くないことが起きるのではないか、といつもびくびくするようになっていた。
M医師は、僕を内分泌の研究に携わっている看護師のダフニーに紹介した。この新薬の治験では、彼女が色々と教えてくれた。しばらくは前の薬と同じように感じたが、注射は月に1回だったし、それに、インスリン様成長因子のレベル(IGF-1)をコントロールしているようだった。このIGF-1とは成長ホルモンに関連したものらしいが、それまでは聞いたこともなかった。ダフニーがこの薬の注射の仕方を教えてくれたので、僕は家でも自分ひとりで注射できるようになった。自己注射の仕方だが、少なくとも僕にとっては、やり方を覚えるのは容易ではなかった。太い針で刺して薬液を注入するのだが、この薬液がドロッとしていて、すぐには入っていかない。ダフニーが注射する時には何も感じないので、同じように注射する方法を教えてもらった。彼女はさらに、患者を金銭的に援助してくれる会社にもわざわざ連絡をとってくれた。最終的に僕は何も払う必要が無くなった。こりゃ最高だね!
ダフニーはとにかく素晴らしい。実際、彼女は僕の健康に純粋に関心を持ってくれており、よく気にかけてくれるし、それに僕がきちんと薬を継続しているかをしっかり把握するようにしてくれている。
さらに彼女は、僕がこの薬を販売しているメーカーと関係を築けるよう取り計らってくれた。そのため、様々な都市に行って、自分の診断のことや自分が考えていることなどについて話すよう、このメーカーから講演を依頼されている。
病気を持っていると、実は人生がこんなに面白いなんて、誰が想像したことだろう。
僕は、自分の体がすぐに普通の状態に戻っていくのを感じた。腕も脚も痛くなくなって、今までよりも動き回れるようになったし、頻繁に倒れてしまうようなことも無くなった。そして頭がボーっとする感じも(ほとんど)無くなった。また、職場での僕の担当はマルチメディア部門で、火曜日に新刊書を書店に並べる仕事があるのだが、以前はこれに1週間もかかっていたのに、今はたった数時間で終わらせることができるようになった。
2回目の手術の後にガンマナイフ治療を受けたのだが、あれは嫌な思い出だ。頭に金属製のヘルメットをつけて1人で何時間も座らされると、今度は、暗くてMRIの所とそっくりな部屋に連れて行かれる。そして、医師と助手が防音室にいそいそと戻っていくと、彼らは横になっている僕にレーザー光線を発射する。恐怖とはまさにこのことだ!
彼らが防音室で話をしている間、僕は1人、そこで横になっていなくてはならなかった。防音になっていたので、2人が話していた、というのも推測に過ぎず、実際に何が起きているのかは良く分からなかった。すでにご想像の通り、治療が終わるのを待ちながら、僕は泣き始めてしまった。そもそも、この治療自体、初めから恐ろしいものだったし、それに、放射線には色々な作用があり、癌を引き起こすこともある、ということも以前から聞いていた。これが正しい情報なのか僕には分からないが、とても心配だった。だが、ようやく治療が終わると、その夜は病院の上の階で過ごし、テレビを見たりアイスクリームを食べたりできたので、全てが酷いわけではなかった。
そして今はもう、心配はしていない。僕はいまだに先端巨大症だし、これからもずっとこの病気を抱えていくのだと思うが、今は信頼できる人に委ねることができている──ダフニーとC医師が僕にはついているから、大きな安心感があるのだ。
引越しをしてからというもの、しばらくメトロポリス・カフェに行っていなかったのだが、最近、久しぶりに行ってみたら、サルに会った。彼女は、僕が自分の健康に無関心だったから本当の僕がいなくなってしまうようで怖かった、元の僕に戻ってほしいと思った、だから去っていったのだ、と説明した。これには僕も納得した。さよならの理由には、もっと酷いものだってあり得る。
死に対する僕の考えは、良い方向に変わっていったと思う。もう、死を心配しなくなった。死ぬ時が来たとしても、その時はその時だ。後でどうにかできるものではない。先端巨大症なんかにかかっていないに越したことはない。しかし、先端巨大症だからこそ、どこに行っても、僕はこの病気について面白い話ができるのだ。
※Acromegaly Communityは先端巨大症患者とそれに共感する人々のための団体であり、先端巨大症患者への有用な情報提供と支援に尽力している。この活動は先端巨大症に共感する人々によって支えられており、会員は6つの国にまたがる。ウェブページである、Acromegaly Community.com(http://acromegalycommunity.com/)は2009年の夏に開設された。